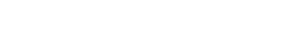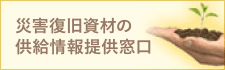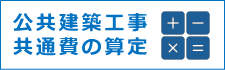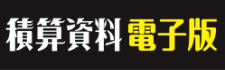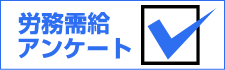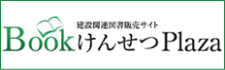- 2019-12-19
- 建築施工単価
季刊 建築施工単価に連載してきた「材料からみた近代日本建築史」のバックナンバーをまとめました。
- 2023-04-13
- 建築施工単価
- 2023-04-03
- 建築施工単価
- 2023-02-20
- 建築施工単価
- 2023-02-16
- 建築施工単価
- 2023-01-30
- 建築施工単価
- 2023-01-30
- 建築施工単価
- 2022-12-05
- 建築施工単価
- 2022-12-05
- 建築施工単価
その1 セメント
近代建築……ここではモダニズム建築と記す……の特徴を整理するときに,こうした“近代という時代”の特有の建築を生み出した背景として,しばしば材料や工法の変革も指摘される。その際,近代特有の建築材料として,よく挙げられるのが鉄・セメント・ガラスの3つの素材である。こう述べると,鉄・セメント・ガラスの3 つの材料自身が近代になって初めて誕生し,使用された材料と考えられてしまうかもしれない。しかしながら,それは勘違い。この3 つの基本的建築材料は,古くから建築にとって重要な材料として使われ続けてきたものである。
…続きはこちら
その2 大谷石 -帝国ホテルとフランク・ロイド・ライト-
日本は木の文化の国で,ヨーロッパのように石の建築はつくられてこなかった,と決めつけてしまうのはいささか早計だ。日本にも独特の風合いをもち,建材として長く使われてきた石材がある。栃木県産の大谷石はもともと石蔵などに使われていたが,フランク・ロイド・ライトが帝国ホテルの設計に際し用いたことで広く知られるようになった。内外装に使われた大谷石には,ライト独自の装飾紋様がふんだんに刻み込まれ,明暗に満ちた,独特の空間がつくりだされることになった。
…続きはこちら
その3 板ガラス生産と近代の日本家屋
一口にガラスと言っても,生活の中には多くの種類とサイズがある。食器,容器,レンズ,服飾品など数え上げれば切りがない。しかし,建築におけるガラスとして最も重要且つ需要が高いのが,窓をはじめとする建具用の板ガラスだろう。ガラスは,平板という形状を得ることによって,それまでの役割を越えて,世界の建築と都市を変えていった。ここでは,そうした板ガラス工業の発達とそれを受容した近代の日本家屋の関係を概観したい。
…続きはこちら
その4 日本における煉瓦建築の盛衰
近年,東京の丸の内に二つの煉瓦造建築が蘇った。一つは明治29年に日本初のオフィスビルとして建てられた三菱一号館,設計は日本建築界の恩人ジョサイア・コンドルである。一度は解体されたが,歴史性のある街づくりを目指す三菱地所の手によって平成21年に竣工時の姿で復元された。もう一つは,コンドルの一番弟子である辰野金吾によって大正3年に建てられた東京駅である。一時は取り壊しが検討されたこともあったが,多くの方々の支持を得て保存が決まり,しかも竣工時の姿に戻して修復された。
…続きはこちら
その5 鉄筋コンクリート
1875(明治8)年,政府主導のもとで開始されたセメントの国内生産が深川工作分局で成功した。これに伴い民間によるセメント製造も開始され,1883(明治16)年9月初めて小野田セメントが生産に成功し,また,1884(明治17)年に深川工作分局の払い下げを受けた浅野セメントも民間として生産を始め,徐々にセメント生産はひとつの産業となるまで成長を遂げた。ちなみに,1897(明治30)年には使用するほとんどのセメントを国産で賄えるほどの生産量となり,その後は,セメントの輸出国へと変貌を遂げ,1937(昭和12)年にはベルギー,ドイツ,イギリスに次いで世界第4位のセメント輸出国となっていたのである。
…続きはこちら
その6 製鉄技術の発達と明治中期までの鉄道建築《前編》
鉄骨構造は、超高層あるいは大規模建築において主流をなす。鉄は現代の都市建築において、不可欠の構造材と言えるだろう。建築材としての鉄は、古代から存在し、パルテノン神殿では石材同士を内部で繋ぐ千切りに用いられ、各地の木造建築においては、釘や金具、建具の一部などに使われてきた。溶かした鉄を鋳造する技術は、中世までに確立されており、建築の補強材や柵、武器や日用品に至るまで多くの用途への対応があった。しかし、建築の主要構造材としては、求められる寸法、強度や供給量が不足していたため、近代に至るまで有効な選択肢にならなかったのである。
…続きはこちら
その6 製鉄技術の発達と明治中期までの鉄道建築《後編》
日本にも古代から各地で製鉄が存在した。良質の山砂鉄を原料とする中国地方のたたら製鉄が代表的だが、砂鉄や鉱石は、近江、美作、東北地方などでも産出されていた。鉄が、武器や建築の補強材など様々に用いられてきた歴史は、ヨーロッパなどと同様のものがある。鎖国状態にあった江戸期においても製鉄技術の理解が進むが、徳川吉宗による洋書の禁緩和で海外からの情報摂取は一層盛んになる。そして幕末以降は、植民地化の危機に臨み、すでに鉄による近代文明を展開させ、錬鉄から鋼鉄への移行期にあった欧米の先進技術から多くを学び実践に移すことが急務になった。
…続きはこちら
その7 鉄骨造による高層オフィスビルの先駆け-日本相互銀行本店と前川國男《前編》
戦後日本の近代建築は1950年代になってようやく本格的なスタートを切ることになった。朝鮮戦争による特需で工業生産が回復し、鉄およびコンクリートによるいわゆる「本建築」が建設できるようになった。戦前、鉄鋼資材統制が施行されたのが1937年である。戦時体制下、また、戦後の復興期を通じて、十数年間にわたり、建築家たちはこうした材料から切り離されたなかで建築を実践するほかなかった。そして、1950年代初頭に竣工した二つの建物、リーダーズダイジェスト東京支社(1951年、設計:アントニン・レーモンド)と日本相互銀行本店(1952年、設計:前川國男)が、こうした戦後の近代建築の幕開けを告げることになった。
…続きはこちら
その7 鉄骨造による高層オフィスビルの先駆け-日本相互銀行本店と前川國男《後編》
だが、地震力の分担率が明確ではなかったとはいえ、十分な余力を見込まれていた耐震壁をいきなり消し去ることはかなりのリスクを伴うものだった。それを横山は、独自の構造形式を採用することでクリアしていこうとする。日本相互銀行本店は、地上2階から地下2階までは梁間14m、桁行7.5mのスパンによる、円形大断面の10本の鉄筋コンクリート柱で架構されている。一方、3階から9階までは、小断面の48本の鉄骨柱が並べられている。横山は前者を「下部構造部」、後者を「上部構造部」と呼ぶ。そして両者をつないでいるのが2階部分で、ここは階高全体を成とするような巨大なトラス梁と板梁が収められている。
…続きはこちら
その8 タイルとテラコッタ《前編》
タイルとは建物の表面に張り付ける薄い板で主に陶磁器質のものを指す。中国渡来の磚(せん)や敷瓦は早くから日本にも導入されていたが、タイルとして入ってくるのは幕末期で、長崎の料亭・花月にはオランダから輸入した色鮮やかなタイル床が今も残っている。洋風住宅の暖炉回りも見せ場のひとつで、日本最古の西洋館であるグラバー邸にはイギリス経由の華やかな“ヴィクトリアンタイル”が使われている。暖炉の他にはサンルームの床材や、風呂場、台所、洗面所といった水回りの内装材として使われてきた。
…続きはこちら
その8 タイルとテラコッタ《後編》
テラコッタとはイタリア語で“焼いた土”を意味し、彫刻などを施した建築装飾用品の総称である。躯体にモルタルで圧着するタイルとは違って、針金などで緊結する外壁装飾材である。日本への導入はアメリカ経由でもたらされた。アメリカにおけるテラコッタの隆盛はシカゴ派の時代で、鉄骨構造を被覆する石の代用品として考案されたものである。懸案であったスカイスクレイパーの高層化と軽量化にとってテラコッタは最良の外装材であった。
…続きはこちら
その9 コンクリートブロック
モダニズム建築に欠かせない建築構造として,鉄筋コンクリート造を挙げることは誰もが認めるものであろう。コルビュジエの建築表現にとっても,この新しい構造としての鉄筋コンクリート造が不可欠なものだったこともよく知られていることである。ところで,コルビュジエがこの鉄筋コンクリート造という新しい建築にふさわしい構造の可能性を学んだのは,オーギュスト・ペレ(1874-1954)であったこともよく知られていることである。このペレは,エコール・デ・ボザールで建築を学んだが,卒業を前に退学し,家族の経営する建築会社に入り,1890年にはコンクリートの建築を設計していたという。
…続きはこちら
その10 ~戦前における鉄骨造建築の発達~
本連載その6(2014年冬号)でみたように,鉄骨を主構造とする建築は,早くから鉄道施設や海軍の周辺で用いられ,官営八幡製鉄所で鉄鋼が国産化される頃から建築界でも注目されるようになる。しかし,煉瓦や木材に代わる新しい構造材への関心は,八幡創業のおよそ10年前に起きた濃尾地震(1891年10月28日)によって高まりつつあった。建築が洋風化する過程では,煉瓦や石材を主構造に充てるケースも少なくなかったが,組積造の建築は,地震に対して脆弱であるため,日本での発達には,そもそも限界があったといえる。しかし,そのことが濃尾地震によって否定しがたい事実として共有されるまで,むしろ煉瓦造が耐震化の具体策として検討される傾向すらあったという。
…続きはこちら
その11 木造乾式構造への挑戦-土浦亀城による第二の自邸《前編》
土浦亀城(つちうらかめき)の第二の自邸は、戦前の日本で盛んに試みられたモダニズムの建築を代表する住宅作品だ。小さな作品ながら、白い箱型の凛々しい姿を、目黒上大崎の一角にいまも映し出している。外観に見える大きなガラス面の背後には吹き抜けの居間が設けられている。高い天井、陽光が降り注ぐ明るい居間は、来(きた)るべき近代生活を象徴する空間だった。玄関から入ると、スキップフロアによって少しずつ床レベルがずらされて、2階の寝室まで内部空間がひと続きになっている。
…続きはこちら
その11 木造乾式構造への挑戦-土浦亀城による第二の自邸《後編》
このような乾式構造は、土浦のみならず、当時の日本の先取的な建築家たちの大きな関心を集め、その可能性がさまざまなかたちで議論されていた。例えば、土浦とも交流のあった建築家市浦健(いちうらけん)はやはり自邸を乾式構造で建て、パネル材の規格化だけでなく窓の定型化にまで踏み込んで設計を行っている。外壁には土浦邸と同様石綿スレートが用いられているが、その取り付け方法は「土浦亀城氏の指示に負う所が多い」と断って、その詳細が報告されている(「一小住宅に関する記録」『新建築』7巻12号、1931年)。
…続きはこちら
その12 戦後建築に見るタイル -巨匠たちのタイル作法-
1950年代初頭,戦後のスタートを飾るにふさわしい三つの建築が誕生して建築界の話題を集めた。『リーダーズ・ダイジェスト東京支社』(1951年)と『日本相互銀行本店』(1952年),そして『日活国際会館』(1952年),いずれも日本建築学会賞を受賞した建築である。
…続きはこちら
その13 メタルラスと鉄鋼コンクリート
建物の外壁は短期間で施工できる窯業系のサイディングが普及したことによって,モルタル仕上げが大きく減少した。ところが近年,左官職人が鏝(こて)から創り出すモルタルの独特な風合いが脚光を浴びるようになり,その下地に用いられているメタルラスの需要が伸びているという。
…続きはこちら
その14 アントニン・レーモンドの打放しコンクリート 「霊南坂の家」から「群馬音楽センター」へ
チェコ出身の建築家アントニン・レーモンドは1919(大正8)年の大晦日,フランク・ロイド・ライトとともに来日した。ライトの設計事務所スタッフとして,帝国ホテル建設の現場監理を行うためだった。ライト離日後も日本に残り,日本で自らの事務所を主宰し,戦時中は一時アメリカへ戻るが戦前・戦後を通じて数多くの作品を日本に残した。日本の伝統的建築から多くを学び,軽井沢の夏の家など丸太を多用した木造建築などでよく知られている。
…続きはこちら
その15 銘木と合板
明治期以降,わが国では,次々と欧米の建築様式を取り入れた洋風意匠の洋館を建ててきた。そのため,伝統的な和風意匠の建築よりも,洋館こそ,巨額が投じられ,さまざまな新しい材料や技法を積極的に取り入れたものであると考えられ,わが国の近代以降の歴史の生き証人として文化財にも指定されてきた。
…続きはこちら
その16 敷床材-消えたゴムタイル-
日本における近代以前の住いの床は,身近な自然材を利用していた。民家では古くは土座に藁(わら)や筵(むしろ)を敷くところから始まり,竹簀(たけす)の床に筵を敷いて生活するようになり,縦引きの大お鋸がの発達する14~15世紀には,板材が張られるようになったと考えられる。
…続きはこちら
その17 コンクリート外壁面における塗装仕上げの挑戦
建物を設計する時,外壁にはどのような材料を使うべきか,建物の用途や構造に加え予算の範囲内で収まるかなどを考え選択しなくてはならない。そして,カタログやサンプルを見ながら,施主の要望や自身の好みだけではなく,周辺環境に影響がないかなど,多角的な観点から検討し数ある仕上げ材料の中から決定した後に,「果たしてこれで良かったのか?」と悩むことが,設計者であれば一度は経験したことがあるのではないかと思う。
…続きはこちら
その18 繊維版(テックス)をはじめとするボード状建材の普及と旧足立別邸
連載の第11回で紹介された乾式構造によるモダニズム建築は,住宅や建築の生産を工業化するというコンセプトに即し,矩形を基調とした外観と立体的でフレキシブルな空間が特徴であった。そこで使われた建材の主役が,工業的に生産された各種のボード類で,これを柱や方立等に取り付けることで壁や天井を作れるため,現場で水を扱う左官仕事やコンクリート工事よりも施工が簡便になり,コストを抑えられるばかりか,断熱性の向上,仕様の改変に対応しやすいなどの利点があった。
…続きはこちら
その19 台所流し材料の変遷-ステンレスに至るまでの道程
フランス第2の都市リヨンに現存する公的住宅団地を訪れたことがある。「工業都市」を提唱したことで知られる,近代を代表するフランス人建築家トニー・ガルニエ(Tony Garnier 1869─1948)が手掛けたレ・ゼタ・ジュニ(Les États-Unis)である。
…続きはこちら
その20 SH-30への歩み-広瀬鎌二による鉄骨造住宅の探求
建築家・広瀬鎌二は,SHシリーズと名付けて戦後復興期から’70年代にかけ,一連の鉄骨造住宅作品を発表した。SHとはスティール・ハウス(Steel House)の略称である。1953年の自邸SH─1から,計画案を含め70を超える作品が設計された。1950年の朝鮮戦争特需をきっかけに日本は敗戦からの復興の歩みを加速させていくが,十分な量の鋼材の供給もまだまだ見込めない時期に,広瀬はいちはやく鉄骨を用いた住宅設計の試みをはじめた。
…続きはこちら
その21 米材の普及と枠組み壁工法の導入の様相
わが国の建築界は,イギリス人建築家のJ.コンドルが“建築界の父”と呼ばれるように,明治期にはイギリスを中心とした欧州の建築をモデルにその導入が開始された。しかしながら,1891(明治24)年の濃尾地震以降,石造・煉瓦造建築の耐震性の模索の中で,煉瓦造や石造の鉄による補強の提案もあって鉄骨造への注目度が高まり,高層建築の追求もあっていち早く木造や石造・煉瓦造から鉄骨造への転換を図っていたアメリカへと建築家の視線が移っていた。
…続きはこちら
その22 天然石模造の人造石
近代の建築は,その建材を人工的あるいは工業的に,しかも大量につくり出すことで発展してきた。製造された鉄,ガラス,コンクリート,タイル,その他ボード類といった建材は,基本的には平滑で人工的な素材感を持ち,近代性を表現する役割を担った。モルタルやペンキの仕上げもその意味で近代的な表現といえる。
…続きはこちら
『材料からみた近代日本建築史』の連載を終えて
2012年秋号から2019年夏号までの8年間にわたり合計22回,筆者を含め7名で「材料からみた近代日本建築史」を連載させていただいた。まずは,連載を終えるにあたって読者の皆様にお礼申し上げたい。さて,本連載の企画は,当初,日本大学教授大川三雄先生が中心となって計画され,現在の日本大学教授の田所辰之助,日本工業大学教授の安野彰,そして,神奈川大学教授の内田青蔵にお声掛けいただき,連載を開始したものである。
…続きはこちら
最終更新日:2020-02-03