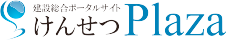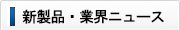- 2015-08-21
- 建築施工単価
外装材としてのタイル
タイルとは建物の表面に張り付ける薄い板で主に陶磁器質のものを指す。
中国渡来の磚(せん)や敷瓦は早くから日本にも導入されていたが、
タイルとして入ってくるのは幕末期で、長崎の料亭・花月にはオランダから輸入した色鮮やかなタイル床が今も残っている。
洋風住宅の暖炉回りも見せ場のひとつで、
日本最古の西洋館であるグラバー邸にはイギリス経由の華やかな“ヴィクトリアンタイル”が使われている。
暖炉の他にはサンルームの床材や、風呂場、台所、洗面所といった水回りの内装材として使われてきた。
外装タイルとしての化粧煉瓦が最初に紹介されたのは1895(明治28)年に開催された内国勧業博覧会においてである。
そこに日本煉瓦製造による“張付化粧煉化石”が登場、前途有望な製品として評価されたことから、
大阪窯業や備前陶器などの会社でも製造に取り組むようになった。
化粧煉瓦とタイルの相違は厚みの違いで、“積む”と“張る”の違いといっても良い。
境界が曖昧なため様々な名称が使われてきたが全国的に統一されるのは
1922(大正11)年の東京平和博覧会の会場に「タイル館」が設けられた時からである。
早くからタイルへの関心を示した建築家は武田五一である。
20世紀初頭のヨーロッパに留学し、
フランスのアール・ヌーボーやオーストリアのゼセッションを、そしてイギリスのアーツ&クラフトなどを直接体験した武田は、
世紀末建築の中に色づくタイルの魅力に早くから惹かれていた。
元々、製陶にも親しむ陶芸好きでもあった。
初期の作品である「名和昆虫研究所記念昆虫館」(1907年)は、
木造煉瓦壁ながら切妻部分を除く壁面の全てに外装タイルが張られた“総タイル張り”としては日本最古の建築である。
「京都府図書館」(1910年、写真-1)では
O・ワグナーを想起させる金色をあしらったウィーン・ゼセッション風の外観意匠が試みられている。
この時、武田に指名されたタイル職人の久田吉之助は、1904(明治37)年に「被覆煉瓦」の特許を取得、
その後もタイルの改良を進めて建築タイルの歴史に大きな足跡を残した。
新しいデザインを模索していた武田にとって、平坦な面の構成を実現する上でタイルは格好の素材であった。
武田が東京本郷に設計した「求道会館」(1915年、写真-2)もタイルの魅力が活かされた作品で、
煉瓦造のロマネスク様式にもかかわらず軽快な雰囲気を醸し出している。
「東京駅」(1914年)は日本最大規模の煉瓦造であり、大規模建造物の煉瓦造としては末尾を飾る建築でもある。
当初は鉄筋コンクリート造も検討されたが、辰野の煉瓦への強い想いから煉瓦造が採用された。
その美しい外装には張付化粧煉瓦(小口平タイル)が用いられている。
これだけの規模の建築に国産の化粧煉瓦を用いたのは初めてのことで、
日本の近代建築の外装が化粧煉瓦へ、さらにタイルへと変化していく契機となった。
この仕事を請けた品川白煉瓦会社にとっても初めての経験で、東京駅における張付化粧煉瓦タイルの大々的な採用が、
他のタイルメーカーを刺激し、業界全体が技術の向上と量産体制に取り組むことになったのである。
ビルブームとタイル
外装材としてのタイルが広く普及するきっかけとなったのは鉄筋コンクリート造の登場である。
関東大震災以後、日本の建築は煉瓦造からRC造へと急激な変化を見せた。
表情豊かな煉瓦と比べるとRC造の仕上げ面は無表情、無機質であることから、タイルが外装材として着目されることになったのである。
「三井物産横浜支店」(1911年、写真-3)は日本初の全鉄筋コンクリート造のオフィスビルであるが、
外装をタイルで仕上げた初めての建築でもあった。
三菱煉瓦街は1号館(1894年)から13号館までは煉瓦造、14号館(1912年)以降のビルにはRC造が採用され、
外壁面には赤い小口タイルが使われるようになった。
1918年には曾禰中條建築事務所が設計(内田祥三が構造を担当)したSRC造の「東京海上ビルディング」が誕生し
“ビルディング”という呼び名の先駆けとなった。
さらに1923年に「丸ビル」と「郵船ビル」が完成、その後はRC造の躯体に白タイルを身にまとったビルが続々と建ち並んだ。
第1次世界大戦後の好景気がいわゆる“ビルブーム”を巻き起こし、同時に新たな建築仕上げ材の出現を招いたのである。
丸の内には赤煉瓦街の“一丁ロンドン”に対し“一丁ニューヨーク”と呼ばれる白く明るい街並が形成されるようになった。
“明治は煉瓦、大正はタイル”の時代である。
大正期に活躍した建築家の中にはタイルに対し強い関心を抱く人が多い。
小規模ではあるが、
渋沢栄一の王子の邸宅「曖依村荘」に残る「晩香廬」(1917年、写真-4)と「青淵文庫」(1925年、写真-5)は
大正期に特有の静謐な雰囲気を色濃く伝える作品である。
清水組の技師長であった田辺淳吉の設計による工芸品のような建築、
前者は木造、後者はRC造であるが、共にきめ細やかな扱いによってタイルならではの魅力を発揮させている。
スクラッチタイルとテラコッタ
“引っ掻き傷”の付けられたタイルのことをスクラッチタイルという。
時には“スダレ煉瓦”などと呼ばれることもあり関東大震災後に広く使われるようになった。
流行の引き金となったのは近代建築の巨匠F・L・ライトの設計した「帝国ホテル旧本館」である。
帝国ホテルは、歴史主義とは異なった形で、建築のもつ芸術性、特に空間の魅力を、実作によって示した点に歴史的な意義がある。
一方、その異様な外観でも人々を驚かせた。
RC造にスクラッチタイル、要所に大谷石とテラコッタでアクセントを付けた建築は、ライト作品の中でも特に装飾性の高いものである。
この作品によって、大谷石が建築の外装材として脚光を浴びるようになったことはよく知られているが、
スクラッチタイルとテラコッタの流行にも拍車をかけた。
ここに約400万丁のスクラッチタイルとテラコッタが使われたため、
愛知県常滑市に「帝国ホテル煉瓦製作所」という直営工場が造られた。
ライトから工場に対する指示とともに、
「スダレ煉瓦」(スクラッチタイル)の実物見本と、間仕切り壁用の軽量煉瓦である「穴抜き煉瓦」の図面、
さらに“特殊煉瓦”と書かれたテラコッタ用の木製の原型見本が届けられたという。
ライトの新材料への挑戦の熱意がうかがえる。
帝国ホテルの完成後、この直営工場を引き継ぐかたちで設立された会社が伊奈製陶である。
タイルの欠点は製品に“焼きむら”が出て、何割かは無駄になってしまうことであった。
しかし、スクラッチタイルは焼きむらがほとんどなく無駄が生じない。
こうした経済的な理由と、陰影のある独特の肌合いが支持された理由であろうか、
関東大震災後から昭和戦前期にかけて多くの建物に採用された。
東京大学本郷キャンパスの震災復興に取り組んでいた内田祥三は、
材料の節約を意図して構内の主要な建物全てをスクラッチタイルのゴシック風でまとめあげた。
内田はスクラッチタイルの経済性と意匠的魅力を世に知らしめた功労者のひとりである。
材料から見た近代日本建築史 その8 タイルとテラコッタ《前編》
材料から見た近代日本建築史 その8 タイルとテラコッタ《後編》
大川 三雄(おおかわ みつお)
1950年群馬県生まれ。
日本大学理工学部建築学科卒、同大学院理工学研究科修士課程修了、現在、日本大学理工学部教授、博士(工学)。
主な著書に「近代日本の異色建築家」(朝日新聞社)、「日本の技術100年 6・建築土木」(筑摩書房)、
「近代和風建築 -伝統を超えた世界-」(建築知識社)、「図説 近代建築の系譜」(彰国社)、
「建築モダニズム」(エクスナレッジ)、「図説 近代日本住宅史」(鹿島出版会)など。
【出典】
季刊建築施工単価2014年夏号
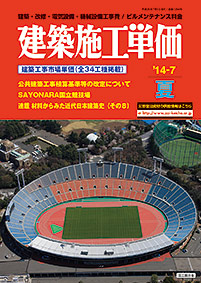
最終更新日:2024-10-30
同じカテゴリーの新着記事
- 2023-04-13
- 建築施工単価
- 2023-04-03
- 建築施工単価
- 2023-02-20
- 建築施工単価
- 2023-02-16
- 建築施工単価
- 2023-01-30
- 建築施工単価
- 2023-01-30
- 建築施工単価
- 2022-12-05
- 建築施工単価
- 2022-12-05
- 建築施工単価