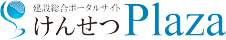- 2023-04-03
- 建築施工単価
ウィーン世紀末
ウィーンは、19世紀的な建築から20世紀的な建築への転換点を示す都市としても有名だ。
すなわち、過去にあった様式に基づいて建築が設計された時代から、目的とする機能や建設する上での必要性に即して建築の形が決定される時代への移行が19世紀末に始まる。
そうした転換の好例とされる作品が、ウィーンにはいくつもある。
例えば「ゼツェッション館」(1898年)がある。
ここには古代ギリシアやローマの建築にあるような形の柱も、中世のウィーンを連想させる装飾も見られない。
飾り気がない壁に、側面から正面にかけて、図案化された植物が繊細なタッチで描かれている。
正面の中央部ではそれが金色によって施され、上部で浮き上がって蔓のような形となり、最頂部では立体化されてドームを形成している。
金色の球形が4本の小塔の間にはめ込まれているわけだが、支持されているというよりも天に昇るものをつなぎ止めているようであり、月桂樹のレリーフの隙間からは向こうの空がのぞく。
それまでの建築の重々しさとは随分と違った姿に映る。
建物は、画家のグスタフ・クリムトをリーダーに1897年に旗揚げされた「ウィーン分離派(ゼツェッション)」の活動拠点として建設された。
設計者は創設メンバーの一人である建築家のヨーゼフ・マリア・オルブリッヒで、金色のドームなどの特徴はクリムトのスケッチに倣っている。
ここでは自然を観察して描いたモチーフが、平面から立体へと展開され、建築全体の性格を形づくっている。
観念が現実となって立ち上がったようであり、その変換の回路は社会的というよりも個人的だ。
過去に客観的に存在した様式を基礎とするのとは、正反対の設計の成果がお目見えしたのである。
ウィーンにおける公的な芸術の発表や発注を牛耳っていたウィーン造形芸術家組合から「分離」して、新たな展示の場を求めた彼らにふさわしい造形だといえる。
しかし、これは美に奉仕するものであって、社会の必要に応えた20世紀の建築に直結しないのではないかと思われるかもしれない。
それでは、オットー・ワーグナーはどうだろうか。
クリムトとは親子ほどの年の差があるが親しい友人であり、クリムトが1918年に没した時には大いに嘆き悲しんだ。
自身も同年に世を去るのだが、国内外に与えた影響力は、50歳を超えた1890年代からこの時まで上昇する一方だった。
1894年にウィーン美術アカデミー建築学科教授に迎えられたオットー・ワーグナーは、就任演説において歴史的な様式の使用を非難し、「建築は同時代の生活状況や建設方法を表現しなければならない」と語った。
こうした考え方をまとめた書籍が『近代建築』で、1896年の刊行から版を重ねてヨーロッパで広く読まれ、新たな建築造形の可能性を理論面から後押しした。
アドルフ・ロースの名も欠かせないだろう。
実作もさることながら、舌鋒鋭い批評で知られる。
1898年の『ポチョムキン都市』において、歴史的な様式に根ざした建築が建ち並ぶウィーンを張りぼての都市に例えたように。
1908年に書かれた『装飾と犯罪』における「装飾は犯罪である」という一文を知る人も多いに違いない。
世紀末の2人の建築家
このような19世紀末からの流れが一つになり、それまでの形骸化した様式のパッチワークに代わって、モダニズムの建築が成立する。
ウィーンの建築の全体をそんな一方向の発展過程としてまとめられたら明快なのだが、そうでもないから、この街の建築は面白い。
第一、連載の前々回と前回で見たように、19世紀後半にウィーンの市壁の解体に伴って整備された環状の大通りである「リングシュトラーセ」に沿って建てられた公共施設が「様式の博物館」であることは、過去の形の抜け殻が無定見に並んでいることを意味しない。
そのようにつくられた全体も、それぞれに選ばれた様式も、市民社会における生き生きとしたメッセージを発しているのだ。
それに、オットー・ワーグナーやアドルフ・ロースの言葉は、機能主義的、実用主義的な建築を生み出すのに貢献したわけだが、彼らの作品にはそれだけに回収されない発見がある。
まずはオットー・ワーグナーから、ウィーンに残された作品を見ていこう。
オットー・ワーグナー
「ショッテンリンク23番地の集合住宅」(1877年)は30代の時の作品で、リングシュトラーセに歴史主義的な建築が完成していく頃に建てられた。
ここにも過去の様式が使われているが、下部の荒石積の扱いは軽快である。
通常のような1階部分だけでなく、2階部分にも用いられ、形は長方形の連なりという方が近い。
このような歴史的な要素の変奏が、三角形の青と白のタイルを組み合わせた斬新な中間部の外壁と同等の重みとなって、調和を生んでいる。
全体に感じられるのは建物を下部から積層した重々しさではなく、都市と向き合う外面をキャンバスに見立てたかのような軽妙さである。
こうした志向が、中間部をルネサンス様式としながらも店舗の入る1・2階と屋上のペントハウスにガラスを露出させた「アンカー・ハウス」(1895年)などを経て、「マジョリカ・ハウス」(1899年)を生み出すことになる。
正面をマジョリカタイルで覆っていることから、この名で呼ばれるようになった。
柄付けされた薔薇の花々が、建築のキャラクターを決定付けている。
咲き誇る花の形は、どれも少しずつ違う。
それらの間に風のような曲線が走って、命あるものの力と儚さを一層強めている。
こうした印象を与えているのは表皮の意匠であり、それは通常、建築的な要素とされる柱や窓などに直接はかかっていない。
それにしても、すぐに散りゆく花々のグラフィックが建物の最大の個性であるということは、永続性を表明するはずの建築というものに対する裏切りではないだろうか。
この賃貸住宅は、ウィーン世紀末の精神を建築に持ち込んで、大胆である。
それが単なる一過性のファサードデザインに終わっていないのは、導入された同時代的な感覚が、建築の歴史を照らし出しているからだ。
思えば、古代ギリシアのコリント式の柱頭はアカンサスの葉に由来するものではなかったか。
ここにおける図柄も、建築を伝統的に飾ってきた列柱の秩序と無縁ではない。
さらにタイルによる被覆も、構造体を磨き上げられた石材で覆い、都市に対する表情をつくってきた建築の歴史の延長上にあるといえる。
隣に設計した「メダイヨン・ハウス」(1899年)も、柔らかいもの、束の間のものをテーマに据えている。
柱頭にあたる位置に9個のメダイヨン―円形や楕円形の飾り板―を配し、上下に装飾を付加して、壁面の全体に繊細な秩序を与えているのだ。
上部で二手に分かれる葉は壁面から自立して見える。
細やかなその先は微風に揺れた姿で、じっと見ていると、こそばゆさが襲ってくる。
下部のリボンも、軽快なものが吊り下げられ、重力によって垂れているかのようだ。
絵画や工芸といった要素に重要な役割を負わせることによって、衣服やアクセサリーのように身体にまとう感覚が表現されている。
それは建築の様式に立てこもり、固く永続的なものによって身体を保護しようという精神からは遠く離れている。
メダイヨンの内側には、ウィーン分離派の創立メンバーであるコロマン・モーザーによる乙女の横顔が描かれている。
変わりゆく一瞬の表情が切り取られ、メダイヨンという古典的な要素の中に置かれることで、日常が神話化され、形骸化した様式はそれが誕生した瞬間のように生き生きとしたものへと解体される。
このようにオットー・ワーグナーは、ものづくりの集積であるという建築の本性を再認識することによって、通常であれば建築によっては不可能だと思われる感覚を喚起させることに成功したのである。
部材の接合部が装飾化された「カールスプラッツ駅」(1899年)、花崗岩や白大理石の外壁をボルトで留めてその頭をアルミニウムで仕上げるなどした「ウィーン郵便貯金局」(1912年)、都市の骨格と向き合う「カイザーバード水門監視所」(1907年)、ミニマルな「ノイシュティフトガッセ40番地の集合住宅」(1911年)と、以後の作品における建設方法の表現は、工芸的なものから工業的なものへと変化していく。
オットー・ワーグナーは同時代の市民の感情を取り込みながら、都市に向き合う規律を求め続けた。
アドルフ・ロース
アドルフ・ロースの「ロース・ハウス」(1910年)は、いわくつきの建物だ。
建設が進み、様式的でない上部があらわになると市民から反対運動が巻き起こる。
議会でも論議を呼び、建物は設計者の名で通称されるようになった。
けれど、今になって見ると、市街地の壁面線を生かした姿は、選択した様式によって個別の建物に凹凸を与えるような設計より、よほど誠実に思える。
下部の大理石が正面性を強め、ガラスと共に、他に代え難い素材性で都市に向き合っている。
真実を見通してしまうロースらしさは「アメリカン・バー」(1908年)にも健在だ。
内装は過去の様式によりかかっていない。
黄褐色の大理石を用いた天井、黒い大理石の柱と梁、マホガニーの壁といった構成によって、素材そのものが堅牢な暖かみをつくり出している。
空間の幾何学性は、片側の鏡に映し出されることで完成に至る。
イリュージョンも現実であることを教える手付きは、ロースの文章の諧謔的な率直さに通じる。
説得力のある表層は前回までの様式的、象徴的なものに代わり、このように工芸・工業的、直接的なものによって目指されるようになった。
生き生きとしながらも永続的なものが、人々に共有可能でありながら個別的な建築をとおして、引き続き追求されたのだ。

倉方 俊輔-KURAKATA Shunsuke-
1971年東京都生まれ。建築史家。大阪公立大学教授。
早稲田大学理工学部建築学科卒業、同大学院修了。博士(工学)。
近現代の建築の研究、執筆のほか、日本最大の建築公開イベント「イケフェス大阪」実行委員会委員を務めるなど、建築の魅力的な価値を社会に発信する活動を展開している。
著書に、『建築家・石井修―安住への挑戦』(共編著、建築資料研究社、2022)『京都近現代建築ものがたり』(平凡社、2021)、『東京モダン建築さんぽ』(エクスナレッジ、2017)、『伊東忠太建築資料集』(監修・解説、ゆまに書房、2013-14)、『吉阪隆正とル・コルビュジエ』(王国社、2005)など多数。
日本建築学会賞(業績)、日本建築学会教育賞(教育貢献)、グッドデザイン・ベスト100ほか受賞。
【出典】
建築施工単価2023年冬号

最終更新日:2023-04-07
同じカテゴリーの新着記事
- 2023-04-13
- 建築施工単価
- 2023-04-03
- 建築施工単価
- 2023-02-20
- 建築施工単価
- 2023-02-16
- 建築施工単価
- 2023-01-30
- 建築施工単価
- 2023-01-30
- 建築施工単価
- 2022-12-05
- 建築施工単価
- 2022-12-05
- 建築施工単価