- 2019-01-21
- 積算資料
キリスト教建築の誕生
永遠の都ローマ。
だが古代ローマ帝国も,もちろん永遠に繁栄したわけではなかった。紀元後3世紀,4世紀頃になると,東方からの移民たちが大挙してヨーロッパに押し寄せた。その少し前の2世紀には最盛期を迎えていたはずのローマ帝国は,異民族の流入とともに,その基盤を大きく揺さぶられていくことになる。
激動の時代を迎えたローマ帝国において,ひとつ重要な政治決定がなされた。それがキリスト教の公認,そして国教化である。一転してそれまで信仰されていたローマの神々への信仰が禁じられ,代わりにキリスト教の信仰が奨励されることになった。ローマの神々に捧げられた神殿建築は法で禁じられた存在になり,新たにキリスト教の聖堂建築が建設されていくことになったのである。
「西洋建築史」の教科書では,この時代の建築を「初期キリスト教時代の建築」と呼ぶのが一般的だ。古代ギリシア・ローマの神殿建築の時代が終わり,今度はキリスト教の聖堂が建設される新たな時代の到来である。この時期,開発されたキリスト教建築の新しいビルディングタイプには,長方形平面の「バシリカ式」と,円形(もしくは多角形)平面の「集中式」があると,教科書にも書かれている。
集中式のキリスト教建築の代表格のものとして,(写真-1)のサンタ・コスタンツァがある。
中央にドームをいただく円形平面の建築で,ドームを支える柱が2本ずつペアの,ほっそりとしたコンポジット式の円柱になっているところが,優雅で美しい。この建物は,キリスト教を公認したローマ皇帝コンスタンティヌス1世が,娘のコンスタンティーナ(354年没)の墓廟として建設したと考えられている建物で,最初期のキリスト教建築としてきわめて重要な建物である。
しかし本稿では,サンタ・コスタンツァと同じ敷地に立つ別の教会堂,サンタニェーゼ・フオーリ・レ・ムーラに注目してみたい。
この土地にはもともと,西暦304年にわずか13歳の若さで殉死したと伝えられる聖女アグネス(サンタニェーゼ)の地下墓所があり,彼女に捧げられた巨大な聖堂が建てられていた。サンタ・コスタンツァはこの聖堂に接続する複合建築となるように建てられたようである。しかし聖アグネスの聖堂はしだいに廃墟化してしまい,7世紀頃になって,少しだけ離れたところに現在のサンタニェーゼ・フオーリ・レ・ムーラ聖堂(写真-2)が建設された。
中世ローマのスポリア
ローマというと,古代の遺跡や,ルネサンスからバロックの時代に建設された壮大なモニュメントばかりに目が行きがちだが,この聖堂は中世の建築である。じつはローマでも,他にもいくつもの中世のキリスト教聖堂を見ることができるのだが,そこには共通して興味深い特徴がある。それは,建築部材の再利用が顕著に見られるという点である。有り体に言ってしまえば,古代の遺跡から柱の部材を奪い取ってきて再利用しているのだ。
古代ローマの円柱のことを,ルネサンスの建築家たちは「オーダー」と呼んだ。そして「オーダー」にこそ,建築美の秘密があると考えたのである。ルネサンスの建築家は,古代の円柱デザインを正確に写し取り,またそのプロポーションの秘密を探り,古代とそっくりの,あるいは本物よりも美しい円柱をつぎつぎに彼らの建築デザインに取り込んでいった。それは,古代の建築デザインを分析し,抽象化することによって,いわば観念のなかの建築デザインへと高めていく作業であった。建築デザイン理論と呼んでもいいだろう。
しかしサンタニェーゼ・フオーリ・レ・ムーラ聖堂(写真-2,写真-3)を見ると,中世の建築家たちは,ルネサンスの建築家たちとは異なる態度で,古代の円柱に対峙したことがわかる。彼らは古代の円柱を抽象化してデザイン理論を構築するのではなく,円柱そのものを実体として再利用したのだ。周りを見渡せば,使われなくなった廃墟がいくらでもあり,そこには無用の長物となった円柱やその柱頭彫刻が無数に転がっていた。彼らはそれらを運んできて,新しい建築で再利用したわけである。
たとえば(写真-3)の3本の柱を見れば,これらの円柱のシャフトに,それぞれ異なる色合いの大理石が使われていることがわかるだろう。その仕上げも,両側の2本は滑らかに磨き上げられているのに対し,中央のものはフルーティング(縦溝)の彫刻が施されており,まったくバラバラである。柱頭の彫刻も右側の二つは同じ遺跡から運んできたのか,ほぼ同一のコリント式柱頭に見えるが,左側のものはコンポジット式で,これまた統一されていない。
このきわめて実用的なやり方を,ルネサンス人たちは「スポリア」と名付け,批判した。古代盛期を理想とするルネサンス人にとって,古代末期から中世にかけては「衰退の時代」であった。それがゆえに,この時代には優れた彫刻を制作する職人がおらず,「仕方なく」部材再利用を行ったと考えたわけである。その結果,ルネサンス人が崇敬した古代の遺跡は,さまざまな遺物を剥ぎ取られ台無しにされてしまったと,彼らは批判したのだった。ラテン語のスポリア(spolia)は,英語のスポイル(spoil)の語源となった言葉で,元々は動物の毛皮を剥ぎ取る等の意味を持ち,転じて「駄目にする」「台無しにする」などの意味を有するようになった言葉である。ルネサンス人は,部材再利用(スポリア)を,古代の遺跡を廃墟化させた諸悪の根源と考えたのだった。
たしかに,古代末期から中世の前半にかけて,ヨーロッパ全体の経済状況はあまり芳しくなかったし,それゆえ,ローマ帝国最盛期のような壮大なモニュメントの建設プロジェクトは,ほとんど存在しなかったといっていいだろう。だが,経済が絶好調で,新築の巨大プロジェクトを次々に建設できる時代にだけ建築の名作が生まれるかといったら,そんなことはないはずだ。
統一性か? 多様性か?
ルネサンス人は,中世人による部材再利用(スポリア)を,それが古代遺跡を台無しにするという観点から批判したわけだが,おそらく,さまざまな部材再利用から生み出される,つぎはぎ的で統一感のない建築空間にも我慢がならなかったのだろう。ルネサンス人たちは統一感のある秩序だった建築空間を好んだ。それに対して中世人たちは,その多様なデザインや石材の色合いや質感を賞賛したといえるだろう。
たとえば,ローマのテヴェレ川西岸に位置するサンタ・マリア・イン・トラステヴェレ聖堂は,ローマでも最も古い歴史を有するキリスト教聖堂のひとつだが,現在の建物は12世紀前半に建て替えられたものと考えられる。このインテリアでもまた,古代の円柱の多様なスポリアが堪能できる(写真-4)。
ここでも円柱のシャフトを構成する石材はさまざまである。よく見ると,柱の太さも少しずつ異なっていることがわかるだろう。柱頭彫刻を見ても,写真に写っているのは2つのコリント式柱頭と4つのイオニア式柱頭だが,それらのディテールまで詳細に観察すると,じつはどれひとつとして同じものはないことがわかる。いわば古代遺跡博物館の陳列品のような状態といえばいいだろうか。
だがこれらのスポリア円柱は,博物館の陳列棚のなかに展示されているわけではない。それ自体が新たな建築の一部となって生まれ変わっているのである。それこそがスポリアの面白さであり,そのことが建築にもたらしている魅力は計り知れない。
もしあなたが建築家で,手元に多様な柱や彫刻があったら,それらをどのような順番で並べるだろうか? 規則性を生み出すように配置する?それともランダムさを強調したデザインにする?ローマでは,本稿でとりあげた2つの中世聖堂の他にも,スポリアの円柱を多用した教会堂を数多く見ることができる。だがそれらをじっくりと観察しても,建築デザイン全体を統合する配置のルールは見いだすことができず,自由で多様性に富んだデザイン,といった印象が強い。だが並べ方を間違うと,もっと乱雑な印象になりそうなところを,うまく踏みとどまって上手にまとめているように思うのは,少し彼らの肩を持ちすぎだろうか。
だがスポリアで古代の円柱を再利用するにあたっては,ただ単にデザインの多様性を称賛すればよいというわけではなかった。あちこちの遺跡の,さまざまな建物で使われていた円柱を集めてきてひとつの建物で使うのだから,そこでは構築的な工夫も必要だった(写真-5)。それらの円柱は,彫刻デザインや大理石の色合いばかりでなく,太さも長さも異なるものであったから,現場での調整は不可避だった。とくに柱の本来の役割を考えれば,長さが異なるというのは致命的で,建物内部の列柱として再利用する以上,すべてが正確に同じ高さにならなければならない。柱頭彫刻の方もすでに見たとおり,バラバラのデザインと大きさのものが使われていたが,それらはある決まった形式を有するデザインなので,こちらは調整のしようがない。そこで,柱の高さ調整は下部で行われたようだ。長さの足りないものについては,足下に礎石が挿入され,高さが微調整される。逆に長すぎる柱を少し切断することも行われただろう。教会堂内の側廊を歩きまわってみると,この苦心の跡が直接的に目に入ってくるので,少し気にならなくもないが,それも建築的な工夫の跡として興味深いものである。
ルネサンスの時代になると,同じ古代の円柱の形式を,建築家たちは建築理論として研究し,実践していくようになる。彼らは,スポリアの再利用ではなく,古代のデザインを正確に再現した真新しい円柱を生産していく道を選んだ。古代遺跡に散乱していた無数の円柱は中世のスポリアであらかた使い尽くされ,さらに16世紀の経済発展とともに建築活動が盛んになったことで,スポリアという選択肢がなくなっていたのかもしれない。その結果,ルネサンスの建物のなかでは,正確にデザインが統一され,大きさもまったく同じ円柱が整然と並ぶことになったのである。
中世建築における多様性と,ルネサンス建築における統一性。建築デザインにおいては,どちらかが正しくどちらかが誤りということはない。だがスポリアがもたらす多様性は,そこに古代の円柱があったから再利用するという実利的な態度と,古代ローマ帝国の物質的記憶を継承するという歴史的な態度が混在していた。多様性は目的ではなく結果としてもたらされたものであり,そのことに筆者は強く惹かれるのだ。
加藤 耕一(かとう こういち)
西洋建築史学者。東京大学大学院工学系研究科建築学専攻教授。東京都出身。1973年生まれ。1995年東京大学工学部建築学科卒業。2001年東京大学大学院工学系研究科建築学専攻博士課程修了,「ゴシック様式の成立過程に関する研究 初期ゴシック時代の建築と社会」で博士(工学)。2004年パリ第4大学(パリ・ソルボンヌ)客員研究員。同年,日本建築学会奨励賞受賞。「時がつくる建築 リノベーションの西洋建築史」で2017年度サントリー学芸賞,2018年日本建築学会賞(論文)を受賞。著書に『「幽霊屋敷」の文化史』(講談社現代新書2009年),『ゴシック様式成立史論』(中央公論美術出版2012年)など。
西洋建築史学者 加藤 耕一
【出典】
積算資料2018年11月号
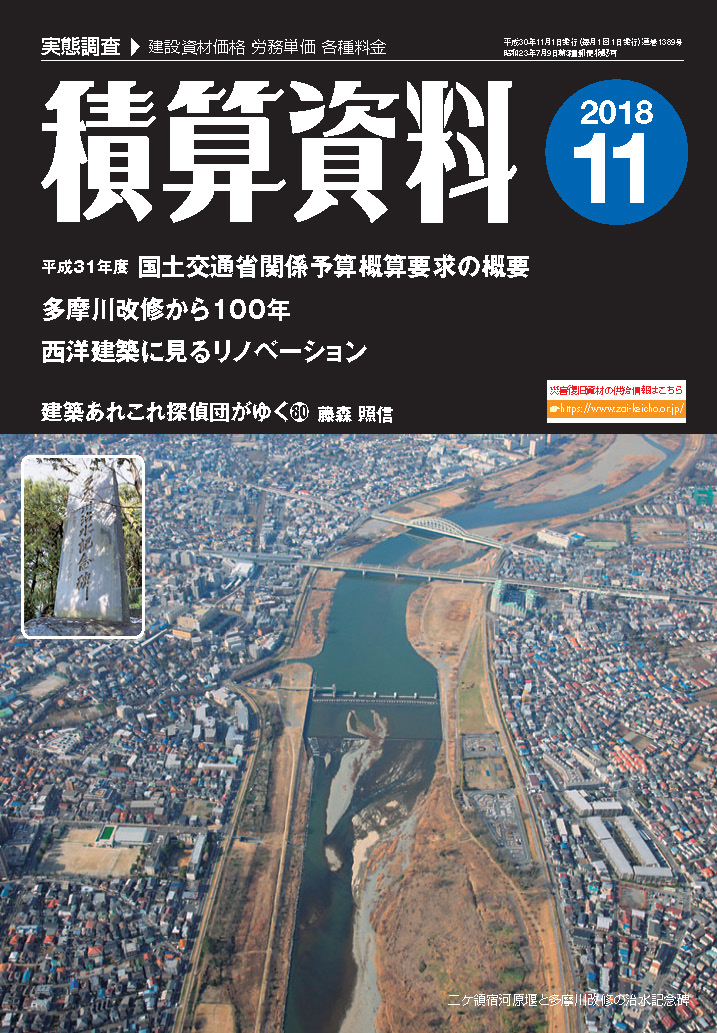
最終更新日:2019-01-07
同じカテゴリーの新着記事
- 2026-01-26
- 積算資料
- 2026-01-05
- 積算資料
- 2025-12-22
- 積算資料
- 2025-12-01
- 積算資料
- 2025-11-25
- 積算資料
- 2025-11-05
- 積算資料
- 2025-10-27
- 積算資料
- 2025-10-20
- 積算資料









