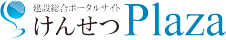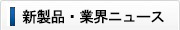- 2025-04-21
- 積算資料
会計検査院は、日本国憲法及び会計検査院法に基づき、国や国が出資している独立行政法人等の法人、国が補助金等を交付している地方公共団体等の会計を検査しています。
このたび、その検査の結果を令和5年度決算検査報告として取りまとめて、令和6年11月6日に内閣に送付しました。
令和5年度決算検査報告に掲記された事項等の総件数は345件であり、このうち指摘事項は338件、指摘金額は計648億6218万円となっています。
指摘事項には「不当事項」、「意見表示・処置要求事項」及び「処置済事項」があり、「不当事項」は、検査の結果、法律、政令若しくは予算に違反し又は不当と認めた事項を、「意見表示・処置要求事項」は、会計検査院法第34条又は第36条の規定により関係大臣等に対して会計経理や制度、行政等について意見を表示し又は処置を要求した事項を、「処置済事項」は、検査において指摘したところ当局において改善の処置を講じた事項を、それぞれ意味します。
令和6年次の検査に先立ち5年9月に策定した「令和6年次会計検査の基本方針」では、重点的な検査項目の一つとして「公共事業」を挙げるとともに、新型コロナウイルス感染症対策及び物価高騰対策に関する各種の施策について、これまでに多額の国費が投入されてきていることなどを踏まえて、適時適切に検査を行うなどとしていました。
そして、検査の結果、検査報告に掲記された事項には、新型コロナウイルス感染症対策関係経費・物価高騰対策関係経費等に関するもの、国民生活の安全性の確保に関するものなどが含まれています。
指摘事項には、府省等別、事項等別、観点別といった様々な分類があり、公共工事関係の指摘として明確に区分ができるわけではありませんが、本稿では、筆者が選定した公共工事関係の主な検査報告事例について簡単に御紹介いたします。
なお、本稿中の記述は簡略化しているため、詳細は会計検査院ウェブサイト(https://www.jbaudit.go.jp)に掲載している令和5年度決算検査報告本文を御覧ください。
本文には検査報告事例の理解に資する参考図等も掲載しています。
また、本稿中の記述内容については筆者の個人的見解等に基づくものであり、会計検査院の公式見解を示すものではないことを御承知おきください。
なお、各案件の末尾に記載している指摘金額について、国庫補助事業に係る事案の指摘金額は国庫補助金等ベースであり、一つの事案の中に複数件の指摘が含まれている場合は、それらの指摘金額の合計額を示しています。
1 設計・施工に関するもの
これらは、構造物に求められる所要の安全度が確保されていない状態となっていた事態や、基準等を満たした適切な施工を行っていなかったなどの事態です。
国土交通省
【不当事項】
・橋脚の耐震補強の設計が不適切(道路メンテナンス事業)
橋脚の耐震補強の設計業務の委託に当たり、基礎の形式が直接基礎となっている2つの橋脚に係る設計の範囲を橋脚の柱部に限定し、直接基礎となっているフーチングを含めた橋脚全体について耐震性を有するように設計することを指示していなかった。
そして、両橋脚の柱部に作用する慣性力が地震時保有水平耐力を下回ることなどから設計計算上安全であるとして、耐震補強を実施していた。
しかし、両橋脚のフーチングに生ずる断面力である最大の曲げモーメント及び最大のせん断力は、安全とされる範囲に収まっていなかった。
したがって、本件橋脚は、設計が適切でなかったため、地震時に所要の安全度が確保されていない状態になっていて、橋脚全体として耐震性を有していないことから工事の目的を達していなかった。
[指摘金額:7332万円](令和5年度決算検査報告359ページ)
・表土掘削の設計数量が過大(防災・安全交付金(その他総合的な治水)事業)
表土を掘削して処分するなどの表土掘削工について、掘削土量の設計数量を、表土掘削を行う箇所の面積の数量として算出した数値を用いていたが、掘削土量としては面積に厚さを乗ずるなどして算出した体積の数量を用いるべきであった。
このため、表土掘削に係る掘削土量の設計数量は、適正な設計数量に対して過大となっていた。
[指摘金額:182万円](同371ページ)
・根固工の設計が不適切(防災・安全交付金(その他総合的な治水)事業等)
根固工の設計において、根固ブロックの敷設高を変更した際に、必要敷設幅を算定することなく、変更前と同じ敷設幅とするなどしていた。
そのため、本件根固工は、河床の洗掘が進行すると護岸に損傷が生ずるおそれがある状況となっていた。
したがって、本件根固工は、設計が適切でなかったため、護岸の基礎を洗掘から保護できない構造となっていて、本件護岸工、根固工等は工事の目的を達していなかった。
[指摘金額:7646万円(4件)](同344ページ)
・監視制御装置等の設計が不適切(防災・安全交付金(河川)事業等)
監視制御装置等の設備機器等を更新するなどの電気通信設備工事において、設備機器等をフリーアクセス床に据え付けるに当たり、発注者は強度検討資料を作成しておらず、請負人は、施工に当たり、発注者から強度検討資料の提示がない場合に発注者に求めることとされている協議を求めずに、設計基準等を満たした適切な耐震施工を行うなどしていなかった。
したがって、本件監視制御装置等は、設計等が適切でなかったため、地震時に転倒するなどして損傷し、所定の機能が維持できないおそれがある状態となっていた。
[指摘金額:4597万円(4件)](同347ページ)
・水管橋の設計が不適切(社会資本整備総合交付金(下水道)事業等)
独立水管橋等の設計について、設計基準等では橋軸方向及び橋軸直角方向の落橋防止構造を設置することなどとされているのに、橋軸方向及び橋軸直角方向又は、橋軸方向の落橋防止構造を設置するなどしていなかった。
したがって、本件水管橋の通水管等は、設計が適切でなかったため、地震時における所要の安全度が確保されていない状態となっていた。
[指摘金額:2372万円(3件)](同350ページ)
・擁壁の設計が不適切(事業間連携砂防等事業等)待受式擁壁の設計に当たり、衝撃力の算定において、急傾斜地の高さについて、誤って斜面途中の傾斜が変化する地点までの高さとするとともに、水平距離について、誤って擁壁背後の切土の法肩から擁壁背面までの距離としていたため、衝撃力作用時において待受式擁壁に作用する力を過小に算定するなどしていた。
そこで、本件待受式擁壁について、現地の状況を踏まえて、指針等に基づき改めて安定計算を行ったところ、所要の安全度が確保されていない状態となっていた。
[指摘金額:1938万円(2件)](同353ページ)
・護岸の設計が不適切(河川等災害復旧事業等)護岸として築造するブロック積擁壁等の設計に当たり、既設のブロック積擁壁の勾配と同様に設計し、施工していたため、ブロック積擁壁の勾配は、指針に示された擁壁の高さと勾配の関係表に基づき勾配を決定することなどとされているのに、関係表の勾配よりも急な勾配となっているなどしていた。
そこで、本件擁壁について、現地の状況を踏まえて、指針等に基づき安定計算等を行ったところ、滑動に対する安定についての安全率が許容値を大幅に下回るなどしていて、安定計算上安全とされる範囲に収まっていなかった。
したがって、本件擁壁等は、設計が適切でなかったため、所要の安全度が確保されていない状態になっていた。
[指摘金額:1339万円(2件)](同356ページ)
・集水桝の設計が不適切(防災・安全交付金(下水道)事業等)
集水桝の設計に当たり、集水桝17基について、車両等が集水桝の上部等を通行する路肩等に設置しており、集水桝の真上等に自動車荷重が作用する状況となっていて、標準図とは異なる荷重条件となっていたことなどから、実際に作用する自動車荷重等の影響を考慮した応力計算を行うべきであったのに、これを行っていなかった。
そこで、集水桝について、実際に作用する自動車荷重を考慮するなどして応力計算を行ったところ、集水桝17基のうち14基については、側壁や底版のコンクリートに生ずる曲げ引張応力度が、コンクリートの許容曲げ引張応力度をそれぞれ大幅に上回るなどしていて、いずれも応力計算上安全とされる範囲に収まっていなかった。
したがって、本件集水桝14基等は、設計が適切でなかったため、所要の安全度が確保されていない状態となっていた。
[ 指摘金額:784万円(2件)](同357ページ)
・桟橋のウッドデッキの設計が不適切(社会資本整備総合交付金(港湾改修)事業)
ウッドデッキの改修について、請負人が申し入れたウッドデッキの構造変更(改修前と同様に、高波浪時にはあらかじめウッドデッキを取り外すことを前提としたもの)を承諾するに当たり、取り外しが必要となる波浪の高さや発生頻度等の海象条件等について確認しておらず、ウッドデッキを取り付けた状態での波浪による揚圧力がウッドデッキに与える影響を検討していなかった。
そこで、ウッドデッキに作用する揚圧力を考慮して、ウッドデッキのビスに生ずる引張応力等を確認したところ、波浪高2.0m以上の波浪が予想される際にウッドデッキを取り付けたままの場合には、側端以外のビスが破断してウッドデッキが破損するおそれがある状態となることが想定された。
そして、波浪高2.0m以上の波浪が予測される都度、約760枚の板材を固定する約3,600本のビスを引き抜いてウッドデッキを取り外すことなどは想定されておらず、作業費用や作業体制等の面から現実的に困難であると認められた。
したがって、桟橋の歩道部のウッドデッキは、設計が適切でなかったため、波浪による揚圧力により破損するおそれがある状態となっていた。
[指摘金額:1578万円](同362ページ)
・橋台の設計が不適切(防災・安全交付金(河川)事業)
橋りょう工(車両の通行を想定しない人道橋を新橋に架け替えるために、下部構造として直接基礎の重力式橋台2基の築造、上部構造として鋼桁等の製作、架設等を実施したもの)の設計に当たり、下部構造については、既設橋りょうと同等のものとすることとし、これにより施工していた。
しかし、本件橋りょうについて、示方書に基づく落橋防止システムの対策を行う必要がないとして、その検討を行っていなかった。
そこで、示方書に基づいて、必要桁かかり長を算出したところ、施工された本件橋りょうの現況の桁かかり長は必要桁かかり長に比べて長さが不足しており、落橋防止システムの性能が確保されていない状況となっていた。
したがって、本件橋りょうは、橋台の設計が適切でなかったため、上部構造の所要の安全度が確保されていない状態となっていて、橋台及びこれに架設された鋼桁等は、工事の目的を達していなかった。
[指摘金額:596万円](同364ページ)
・側壁護岸の設計が不適切(防災・安全交付金(砂防)事業)
側壁護岸の設計に当たり、前庭保護工、間詰工等について、埋め戻した土砂やブロック積擁壁等の載荷重により主働土圧が生ずるのに、これに対して側壁護岸が安全な構造であるかについて、設計計算を行うなどの基準等に基づく照査を行っていなかった。
そこで、基準等に基づき、主働土圧を算定するなどして側壁護岸について設計計算を行ったところ、左岸側について、設計計算上安全とされる範囲に収まっていなかった。
したがって、本件左岸側の側壁護岸等については、設計が適切でなかったため、所要の安全度が確保されていない状態となっていた。
[指摘金額:365万円](同366ページ)
農林水産省
【処置済事項】
・大型土のうの製作及び撤去に係る運搬土量等の算出について
土地改良事業における土砂運搬費等の算定に当たり、運搬土量等について、要綱等及び土砂条件に基づいてほぐした土量を地山土量に換算する必要があったのに、多くの事業主体において、ほぐした土量のまま算出していたため、運搬土量等が過大に算出されていて、土砂運搬費及び購入費等が過大に算定されていた。
[指摘金額:(直轄事業)866万円、(補助事業)953万円](同317ページ)
【不当事項】
・請負人に設計と相違した施工をさせたため治山ダムの施工が不適切(復旧治山事業)
重力式ダムの設計に当たり、設計図書において、上流側を2か所の水抜きの設置箇所も含めて堤底から2.0mの高さまで埋め戻すこととする埋戻し線を表示し、これにより会社に施工させることとしていた。
しかし、水抜きと水抜きの間について、堤底から1.58mから1.75mの高さまでしか埋め戻されていなかった。
その経緯を確認したところ、施工中に会社と口頭による協議を行い、誤った認識に基づいて、会社にその下端が堤底から1.58mの高さにある水抜きが露出するように施工させ、完成検査においてこれを合格としていた。
そこで、実際の埋戻しの高さが最も低かった堤底から1.58mの部分について、改めて安定計算を行ったところ、堤体の破壊に対する安定が確保されていない状態になっており、工事の目的を達していなかった。
[指摘金額:2139万円](同270ページ)
・防風施設の設計が不適切(水利施設等保全高度化事業)
みかんの風害を防止するための防風施設の設計に当たり、誤って防風生垣の設計を行わないまま本件工事を発注しており、設計図面において防風施設として防風ネットのみを設置することとしていたことから、防風生垣を設置せずに工事を完了していた。
このため、防風ネットのみの減風機能により、みかん苗木が受ける風速を算定すると、必要な減風機能が確保されていない状況となっていた。
したがって、本件防風施設は、設計が適切でなかったため、工事の目的を達していなかった。
[指摘金額:1144万円](同280ページ)
・ため池の機能を廃止するために設置した水路の設計が不適切(農業水路等長寿命化・防災減災事業)
U型水路の設計に当たり、地下水によるU型水路の浮上に対する検討を省略していたが、U型水路の設置箇所の大部分は廃止するため池の底部に当たるため、地下水が滞留して地下水位が上昇しやすい状況となっていた。
そこで、実際の地下水位を調査し、その結果を踏まえて、下流側U型水路について、地下水によるU型水路の浮上に対する検討を行ったところ、必要とされる安全率を大幅に下回っていた。
したがって、下流側U型水路、これに接続する集水桝等は、設計が適切でなかったため、所要の安全度が確保されていない状態となっており、工事の目的を達していなかった。
[指摘金額:526万円](同281ページ)
・覆式落石防護網工の設計が不適切(地方創生道整備推進交付金事業)
法面の落石対策の実施に当たり、安定性等の調査を行うことなく、落石防護網工の工法の一つである覆式落石防護網工により施工することとしていた。
そして、覆式落石防護網工に用いる各部材の設計計算を実施しないまま、縦ロープ及び横ロープの径を決定していたことから、本件覆式落石防護網工は、設計上、所要の安全度が確保されているかを確認できない状況となっていた。
そこで、本件法面について安定性等の調査を実施し、本件覆式落石防護網工に用いる各部材について改めて設計計算を行ったところ、縦ロープは2工区計36本のうち11本の安全率が、横ロープは2工区計6本のうち4本の安全率が、それぞれ必要とされる安全率を大幅に下回るなどしていた。
したがって、本件覆式落石防護網工は、設計が適切でなかったため、落石を防止するための所要の安全度が確保されていない状態となっていて、工事の目的を達していなかった。
[指摘金額:269万円](同282ページ)
・ため池への立入りを防止するために設置したネットフェンスの基礎の設計が不適切(農業水路等長寿命化・防災減災事業)
ネットフェンスの設置に当たり、鋼管基礎が設置される地盤には、設計計算書等において前提とされていた平たんな地盤のほか、ため池周辺の法面が含まれていたのに、これを考慮せずに請負人が作成した詳細図等を承諾していた。
また、詳細図等に示された長さ550mmの鋼管基礎を600mmのものに変更したいとの請負人からの申し出を承諾するとともに、根入れ長を当初の設計よりも短くすることも併せて承諾していた。
そこで、鋼管基礎が設置された地盤の状況及びネットフェンスの設置高さを調査した上で、最大水平地盤反力度が受働土圧強度を上回っていないか、改めて確認したところ、平たんな地盤に設置された鋼管基礎132本中83本、法面に設置された鋼管基礎129本中128本、計211本については、安定計算上安全とされる範囲に収まっていなかった。
したがって、本件ネットフェンスのうち延長計450.0mの区間は、設計が適切でなかったため、風荷重による転倒に対して所要の安全度が確保されていない状態となっていて、工事の目的を達していなかった。
[指摘金額:251万円](同284ページ)
2 積算に関するもの
これは、工事の積算に当たり、誤って補正係数を乗じていたため、工事価格が過大となっていた事態です。
国土交通省
【意見表示・処置要求事項】
・ICT(情報通信技術)活用工事の積算について ICT活用工事における出来形管理等経費の積算に当たり、従来手法による出来形管理等や施工履歴データを用いた出来形管理等を実施する ことなどとしているのに、誤ってICT補正(共通仮設費率等に1.2等の補正係数を乗ずること)を行っていて工事価格が過大に積算されていた。
[指摘金額:(直轄事業)1億7420万円、(国庫補助事業等)1159万円](同376ページ)
3 契約に関するもの
これは、契約額の変更を適切に行わなかったなどのため支払額が過大となっていた事態です。
中日本高速道路株式会社
【不当事項】
・舗装補修工事の施工に当たり配置する交通監視員に係る費用について、実際の工事現場の状況が設計図書に示された条件と一致していなかったのに、設計図書を変更しなかったなどのため、支払額が過大
舗装補修工事の施工に当たり配置する交通監視員に係る費用について、実際の工事現場の規制は、特記仕様書等で示された2交替ではなく、13時間超配置により行われていたのに、設計図書の変更を行わないまま、13時間超配置となっていた1人の者を一律に2人日とした人日数に対して、拘束時間が13時間の者に適用すべき既契約単価を乗じて算出していた。
したがって、このほかの報告書に過大に計上されていた人日数も考慮して本件工事の交通監視員の適正な人日数を算出するなどして諸経費等を含めた適正な工事費を算定すると、支払額が過大となっていた。
[指摘金額:2822万円](同473ページ)
4 事業運営に関するもの
これは、優先して耐震補強を実施する要対策橋りょうの選定に当たり、地震時に緊急輸送道路のネットワークとしての機能に及ぼす影響を十分に考慮していなかったなどの事態です。
国土交通省
【意見表示・処置要求事項】
・緊急輸送道路にある橋りょうの耐震補強の効率的な実施等について
優先して耐震補強を実施する要対策橋りょうの選定に当たり、落橋等防止性能が確保されていない要対策橋りょうがあるのに、落橋等防止性能が既に確保されている要対策橋りょうの機能回復性能を確保するための耐震補強を実施していたなど、地震時に緊急輸送道路のネットワークとしての機能に及ぼす影響を十分に考慮していない事態や、要対策橋りょうが地震時に被災した場合の迅速な応急復旧を実施するための体制が十分なものとなっていない事態が見受けられた。
[背景金額:(直轄事業)70億3867万円、(国庫補助事業等)112億1372万円 等](同382ページ)
本稿で御紹介する検査報告事例は以上ですが、会計検査院ウェブサイトには、御紹介した事例を含む令和5年度決算検査報告の指摘事項等の全文を掲載しています。
過去の検査報告について検索できる「会計検査院検査報告データベース」もございますので、是非御活用ください。
今後とも、検査活動に対する皆様の御理解を深めていただくため、検査結果をできる限り分かりやすく公表するとともに、同様な事態の再発防止のため、様々な機会を捉えて検査結果について説明してまいりたいと考えております。
最後になりますが、国や地方公共団体、国の出資法人等の職員の皆様及び公共工事に携わる関係者の皆様には、これらの検査報告事例を今後の業務の参考にしていただければ幸いです。
【出典】
積算資料2025年2月号
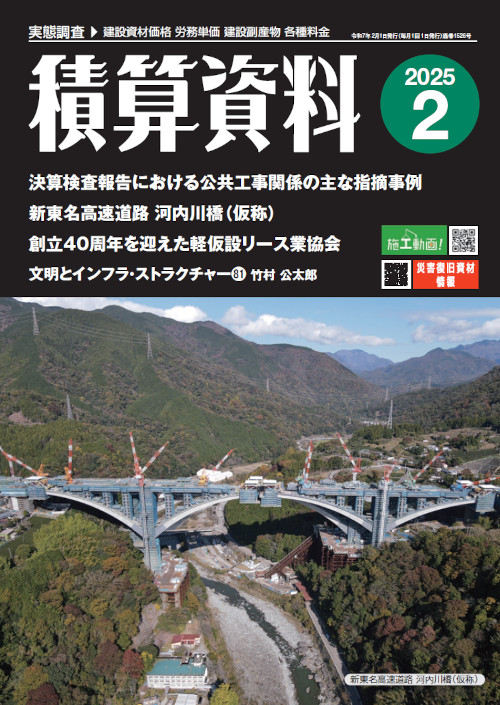
最終更新日:2025-07-04
同じカテゴリーの新着記事
- 2026-02-24
- 積算資料
- 2026-01-26
- 積算資料
- 2026-01-05
- 積算資料
- 2025-12-22
- 積算資料
- 2025-12-01
- 積算資料
- 2025-11-25
- 積算資料
- 2025-11-05
- 積算資料
- 2025-10-27
- 積算資料
- 2025-10-20
- 積算資料