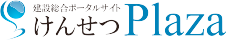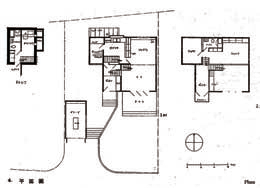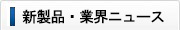建築学科 教授 田所 辰之助
モダニズム導入の旗手として
土浦亀城(つちうらかめき)の第二の自邸は、戦前の日本で盛んに試みられたモダニズムの建築を代表する住宅作品だ。
小さな作品ながら、白い箱型の凛々しい姿を、目黒上大崎の一角にいまも映し出している(図-1)。
外観に見える大きなガラス面の背後には吹き抜けの居間が設けられている(図-2)。
高い天井、陽光が降り注ぐ明るい居間は、来(きた)るべき近代生活を象徴する空間だった。
玄関から入ると、スキップフロアによって少しずつ床レベルがずらされて(図-3)、2階の寝室まで内部空間がひと続きになっている。
https
空間を切り分けながらも全体をつなぐ、こうした立体的な空間の構成もまたモダニズムの大きな特徴だ(図-4、5)。
壁に覆われて、内部は一体となる空間。
木造でありながらこうした空間構成が可能になったのは、
当時「乾式(かんしき)構造」と呼ばれた新たな構造形式が実験的に導入されていたからだ。
土浦は1931年に第一の自邸を設計し建設するが、この第一の自邸から第二の自邸までの4年間に、
俵邸(1931年)、高島邸(1934年)(図-6)など、乾式構造による住宅を計7作品手掛けた。
第二の自邸は、乾式構造による土浦の住宅作品の棹尾(とうび)を飾るもので、その集大成ともいえる。
土浦はこの時期、住宅以外にも銀座トクダビル(1931年)(図-7)、野々宮アパート(1936年)、
強羅ホテル(1938年)(図-8)などを手掛け、日本におけるモダニズム導入の旗手として頭角を現していった。
今回は土浦亀城の第二の自邸を取り上げて、そこに用いられた木造乾式構造について見ていくことにしたい。
土浦は、この乾式構造にどのような可能性を見いだしていたのか。
土浦だけでなく、当時の日本の建築家たちは、日本にモダニズムを定着させるために乾式構造にどのように取り組み、
実践しようとしていたのだろうか。
「鋳物式」から「組立式」へ
乾式構造は当時、「乾式工法」「乾構造」「乾構築」などとも呼ばれていた。
パネルなどを用いて、従来のモルタルや漆喰など、
左官工事を現場で発生させない工法あるいは構造の総称として使われるようになった。
土浦邸(以下特記なき場合、第二の自邸のことを指す)では、木造軸組に対し外壁は石綿スレート板、
内部の壁や天井には当時テックスと呼ばれた植物繊維板が貼り付けられている。
石綿スレート板は耐火防水性能に富み、テックスは高い遮音防湿性能をもつ。
また、内外壁の間の中空層は、断熱のために籾殻で充填された。
工場生産されたボードやパネル類を貼り付けて仕上げる方法は、
現在ではプレハブ工法としてあまりに一般的だが、まさにその先駆けとなる試みだったといえる。
では、設計者の土浦は当時、こうした乾式構造による利点をどのように考えていたのだろうか。
「乾式構造の住宅」という小論のなかで、
土浦はその特徴を「鋳物→組立式」「湿→乾」「工芸→工業」の三つの変化として説明している(『国際建築』8巻3号、1932年)。
まず、「湿→乾」に転換することで、いったい何が変わるのか。
ここで「湿」としてやり玉に挙げられているのは、実はコンクリート構造のことだ。
コンクリート構造が耐火や強度においてたとえ優れていても、断熱や防湿といった点では大きな弱点をもつ。
何よりも、「仮枠と言う不生産的な準備工事を要し、出来た後で取り壊しや改造に不便」と土浦は断じている。
壁体をつくるために型枠を組み、コンクリートを流し込まなければならない。
こうした「不生産的」な作業を必要とするコンクリートの「鋳物式構造」に変わり、
工場であらかじめつくられたボードを貼り付ける「組立式」によって、現場での手間は大きく削減される。
また、手作業に多くを依存する「工芸」的段階から、工場生産による「工業」的段階への移行が可能になる。
文中には「工場製作を多く、現場作業を少なく」と標語のように記されているが、
組立式にすることで工期の短縮とそれにともなう工費節減が図れるのである。
乾式構造とは、こうした鋳物式(コンクリート)から組立式(鉄骨・木造)への、構造形式および工法の転換を象徴する、
当時最新のキーワードだった。
トロッケンモンタージュ・バウ
こうした乾式構造には、当時一つのモデルとなる住宅作品があった。
1927年にドイツのシュトゥットガルトで、ドイツ工作連盟主催による「住居(Die Wohnung)」展が開催された。
その際、市郊外ヴァイセンホーフの丘の一角を敷地としてジードルンクと呼ばれる集合住宅が建設され、
ドイツばかりでなくル・コルビュジエやJ.J.P.アウトなどヨーロッパ各国から前衛的な建築家たちが招聘(しょうへい)され
その腕を競った(図-9)。
このときヴァルター・グロピウスが設計した住宅が「トロッケンモンタージュ・バウ(Trockenmontage Bau)」として紹介され、
その成果が日本へいち早く伝えられていた(図-10)。

図-10 ヴァルター・グロピウス設計による住宅
(ヴァイセンホーフ・ジードルンク、シュトゥットガルト、1927年)
出典:Deutscher Werkbund(ed.), Bau und Wohnung, Akad.Verlag Dr. Fr. Wedekind & Co., Stuttgart, 1927)
当時の『国際建築』誌には「ワルター・グロピユス(原文のママ)の第十七号の家」と題して、
その概要が以下の五つのポイントにまとめられている(『国際建築』8巻3号、1932年)
1) 既成家屋の構造(屋根・壁等)の組織的な改造の必要
2) 材料の経済性と新技術の採用
3) 敷地と空間の合理的経営と組立式乾式建築の導入
4) 機械の組織的計画と合理的な建築計画
5) 短期間の建設による経済上の利点
トロッケンモンタージュ・バウとは、ここに記されている「組立式乾式建築」のことで、
グロピウスの住宅ではZ形の鉄骨柱に、規格化されたボード類を嵌(はめ)込むことで壁体がかたちづくられていた。
平面は正方形で、1.06mを単位とする格子状に分割され、内外装のボード類や窓を設置する際の基準寸法となっている。
煉瓦や石による「既成家屋の」組積造建築から、
近代的な工業生産に対応した新たな建設技術への転換が実験的に試みられたのである。
フラットルーフの箱型の外観とともに、
施工中の鉄骨骨組やコルク板を壁に充填する作業中の写真も合わせて転載されている(図-11)。
日本では当時、鉄骨軸組の住宅は実現できる段階にはなかったが、
伝統的な木造の技術を応用してそれに代替しようとしたのが「乾式構造」の取り組みだった。
ちなみに、グロピウスの住宅では壁厚は157mm、外壁にはアスベスト板(6mm)、内壁にはセロテックス(11mm)を用いている。
この内外壁の間にコルク板(80mm)を挿入し、
このコルク板の両面に、断熱・防音を目的とした空気層(30mm)をそれぞれ設けているのが特徴的である。
材料からみた近代日本建築史 その11 木造乾式構造への挑戦-土浦亀城による第二の自邸《前編》
材料からみた近代日本建築史 その11 木造乾式構造への挑戦-土浦亀城による第二の自邸《後編》
【出典】
季刊建築木施工単価2015年春号
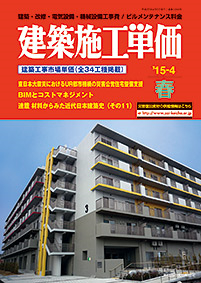
最終更新日:2024-10-30
同じカテゴリーの新着記事
- 2023-04-13
- 建築施工単価
- 2023-04-03
- 建築施工単価
- 2023-02-20
- 建築施工単価
- 2023-02-16
- 建築施工単価
- 2023-01-30
- 建築施工単価
- 2023-01-30
- 建築施工単価
- 2022-12-05
- 建築施工単価
- 2022-12-05
- 建築施工単価