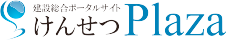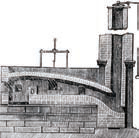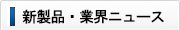- 2015-05-08
- 建築施工単価
准教授 安野 彰
欧米における鉄と建築鋳鉄から錬鉄へ
鉄骨構造は、超高層あるいは大規模建築において主流をなす。
鉄は現代の都市建築において、不可欠の構造材と言えるだろう。
建築材としての鉄は、古代から存在し、パルテノン神殿では石材同士を内部で繋ぐ千切りに用いられ、各地の木造建築においては、釘や金具、建具の一部などに使われてきた。
溶かした鉄を鋳造する技術は、中世までに確立されており、建築の補強材や柵、武器や日用品に至るまで多くの用途への対応があった。
しかし、建築の主要構造材としては、求められる寸法、強度や供給量が不足していたため、
近代に至るまで有効な選択肢にならなかったのである。
状況は18世紀に変わる。
新技術によって主たる構造材としての要件を満たした鉄の生産が可能になったためである。
1735年、英国コールブルックデールのエイブラハム・ダービー2世が石炭コークス高炉による品質の良い鋳鉄の
恒常的な生産に成功する。
古来、製錬には、鉄鉱石から酸素を除くために炭素を用いたが、枯渇しつつあった木炭の代わりに石炭コークスを使う状況ができた。
それに対応する技術革新が蒸気機関を伴って引き起こされ、鋳鉄の量産化が可能となる。
その結果、ダービー2世の息子、ダービー3世は、1779年に世界初の本格的な鉄橋であるアイアン・ブリッジを
近隣のセヴァン川に建設するに至った(図-1)。
なお、その後の鉄生産の拡大には、蒸気機関と鉄道の普及が大きく関係していた。
蒸気機関車の車体、レール、橋梁、駅舎などは鉄の需要を大きくし、それによる技術改良が促され、
蒸気機関の存在が直接貢献したためである。
鋳鉄は、その名の通り、溶融した鉄を鋳型に流し込んで成型することに適していたため、様々な用途に対応した。
構造物では、橋梁、鉄柵、工場等の柱梁や小屋組、窓枠などで用いられたが、当初、建築物では、その防火性能を期待された。
外壁を煉瓦や石造にしても、架構や内部の床が木造であれば、日常的に裸火を使う工場では、出火のリスクを伴ったためである。
そこで、木材を鉄で代替することで、一応の防火を成立させた。
この場合、梁や小梁の間には、鉄板もしくは煉瓦や中空の焼き物でアーチを構成し、床面を石貼りに、
窓枠にも鋳鉄を使用するなどした。
リヴァプールのアルバート・ドック(1839~1845年)は、この種の防火床で施工された事例だが(図-2)、
類例は18世紀末頃からみられるという。
また、鋳鉄製の部材には、その特性を多彩な装飾が施されたことも特筆される。
パリに建設されたサントゥジェーヌ教会(1855年)、パリ国立図書館(図-3・1868年)などは、
装飾的な鋳鉄製の柱やトレーサリーを有する好事例だろう。
また、おおよそ150mの高さで聳えるルーアン大聖堂の尖塔(1876年)も、当時の鋳鉄製である。
一方で鋳鉄は、石炭コークスで製錬されるため炭素量が多く、脆さがあり、引っ張り力には十分対応できないという弱点もあった。
大きな荷重が予測される場合、前記したアイアン・ブリッジのように、鋳鉄を使いつつも、
アーチの形状を採って圧縮強度に対応させる事例が少なくない。
また、一定スパン以上ある鉄道の橋脚では、重量の大きい車体が高速で移動する際に受ける動的な荷重に対し、
より大きな引っ張りやねじれに対する強度が必要とされたのである。
鉄の強度は、含有される炭素量にかかっている。
これが低ければ強度は増すが、炭素を除去するには、
再溶解した鋳鉄や銑鉄を石炭と離して高温を保ち、燃焼・還元する技術が待たれた。
1783年、ヘンリー・コートによるパドル法が考案され、
溶解した鋳鉄(銑鉄)を撹拌しつつ火焔のみを送り込む方法が採られた(図-4)。
いわゆる反射炉による精錬である。
これに、蒸気機関を利用した強力な送風の技術、圧延の技術が加わり、
鋳鉄よりも炭素量が少なく引っ張り強度に対応できる錬鉄の工業生産が実現されていく。
しかし、成型のしにくさを含めた経済性での比較から、すぐに鋳鉄に取って代わるには至らなかった。
したがって、建築物においては、鋳鉄と錬鉄の併用は珍しくない。
1851年、ロンドンでの万国博覧会主会場としてジョセフ・パクストンの設計で出現したクリスタル・パレスもそうした事例である。
同一規格部材によるプレファブリケーションで造られた巨大な柱梁建築は、両者の特性が活かされた事例と見ることもできよう。
また、パリ近郊ノワジエルのチョコレート工場(図-5・1872年)は、ラチス状に組み立てられた鋳鉄と錬鉄の骨組が外観に反映された。
錬鉄は当初、補強部材として局所的に使われていた。
I型の梁を成型するにも高度な圧延技術が求められたが、経済性を伴った量産には、時間を要したためである。
その間、橋梁や建築に用いられた比較的に大型の梁は、プレートやアングル断面の錬鉄をリベットで緊結させて造られていた。
これらは鉄道駅を覆うヴォールト状の大屋根のトラスなどに使われていた。
セント・パンクラス駅の架構は、錬鉄の組み立てにより成立している(図-6・1868年)。
錬鉄は、19世紀の後半までに次第に活用される場面を広げ、1889年に建設されたパリのエッフェル塔では、
地上だけで7,300tという大量の錬鉄が使われる(図-7)。
鋼の登場
しかし、その頃には、すでに炭素量をさらに低下させた鋼材が登場し、フォース橋(1890年)の完成が、その有効性を示していた。
なお、この鋼鉄橋とほぼ同じ時期に竣工したエッフェル塔で錬鉄が多量に用いられたのは、価格検討の結果とされる。
1855年、ヘンリー・ベッセマーが考案した転炉法は、炉内の底から銑鉄へ直接に空気を送り込むことで燃焼温度を上げ、
さらなる炭素の除去を実現し、鋼の時代を導くことになる。
その後改良が重ねられ、圧延の技術も発達し、1880年代には、鋼が錬鉄に代わる存在になりつつあった。
超高層ビルの先駆として、1883年のシカゴで10階建てのホーム・インシュランスビルが建てられたが、
7階以上には、急遽、鋼が用いられることになる。
これは、6階までを鋳鉄の柱と錬鉄の梁で施工していたところ、カーネギー社から鋼の圧延梁が発売されたためという。
鋼材は、高い強度があったがため、必要荷重に対して軽量であった。
それゆえ、強い火災に弱いという鉄の弱点は、鋳鉄などよりも拡大される側面がある。
そのために、シカゴの超高層ビルでは、耐火被覆材としてテラコッタ・ブロックが発達した(図-8)。
シカゴの超高層ビル群が、大火を契機に新築された経緯も関係するだろう。
超高層化にあたっては、このほかにも、エレベータやその安全装置、給排水技術の発達も伴った。
シカゴに始まった鋼の超高層ビルは、ニューヨークのマンハッタンでも高さと華麗さを競い、
摩天楼が林立する巨大都市の風景を生み出すのである。
また、ニューヨークでは、1883年に、ブルックリンの吊橋が完成するが、
これは、鋼のワイヤーを束ねて用いることで成立した画期的なものであった。
20世紀末に至り、鋼材の供給が本格化することで、鉄が建築の主構造としての性能を十分に発揮できる状況が整えられるが、
そうした時代に生まれた新様式の建築においても、材料の特性が反映された。
ヨーロッパの建築では、鉄を意匠の要として用いた建築作品に事欠かず、戦前までの日本と対照的である。
例えば、ベルギーのヴィクトール・オルタやパリで活躍したエクトール・ギマールによるアール・ヌーヴォー建築では、
植物を模した柱、流麗な曲線とシャープな直線などが諸種の鉄材で表現された(図-9)。
ウィーンのオットー・ワグナーは、鉄を含む新素材による構成を内外観の表現の要とした。
ペーター・ベーレンスによるベルリンのAEGタービン工場(1909年)は、鉄による架構の合理的な美しさを印象づけた傑作である。
また、戦後、鋼材による精緻な構築美と厳格な空間性を追求したミース・ファン・デル・ローエの作品群は、
近代建築史上の極点を築くに至る。
材料からみた近代日本建築史 その6 製鉄技術の発達と明治中期までの鉄道建築《前編》
材料からみた近代日本建築史 その6 製鉄技術の発達と明治中期までの鉄道建築《後編》
【出典】
季刊建築木施工単価2014年冬号

最終更新日:2024-10-30
同じカテゴリーの新着記事
- 2023-04-13
- 建築施工単価
- 2023-04-03
- 建築施工単価
- 2023-02-20
- 建築施工単価
- 2023-02-16
- 建築施工単価
- 2023-01-30
- 建築施工単価
- 2023-01-30
- 建築施工単価
- 2022-12-05
- 建築施工単価
- 2022-12-05
- 建築施工単価