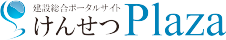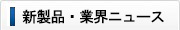- 2024-05-14
- 積算資料
会計検査院は、日本国憲法及び会計検査院法に基づき、国や国が出資している独立行政法人等の法人、国が補助金等を交付している地方公共団体等の会計を検査しています。
このたび、その検査の結果を令和4年度決算検査報告として取りまとめて、令和5年11月7日に内閣に送付しました。
令和4年度決算検査報告に掲記された総件数は344件であり、このうち指摘事項は333件、指摘金額は計580億2214万円となっています。
なお、指摘事項には「不当事項」、「意見表示・処置要求事項」及び「処置済事項」が含まれ、以下、①「不当事項」は、検査の結果、法律、政令若しくは予算に違反し又は不当と認めた事項を、②「意見表示・処置要求事項」は、会計検査院法第34条又は第36条の規定により関係大臣等に対して会計経理や制度、行政等について意見を表示し又は処置を要求した事項を、③「処置済事項」は、検査において指摘したところ当局において改善の処置を講じた事項をそれぞれ意味します。
検査に先立ち令和4年9月に策定した「令和5年次会計検査の基本方針」では、重点的な検査項目の一つとして公共事業を挙げるとともに、新型コロナウイルス感染症対策に関する各種の施策について、医療提供体制の確保、雇用・事業・生活に関する支援等のために多額の国費が投入されていることなどを踏まえて、各事業等の進捗状況等に応じて適時適切に検査を行うなどとしていました。
そして、検査の結果、検査報告に掲記されたものには、新型コロナウイルス感染症対策関係経費等に関するもの、デジタルに関するもの、環境及びエネルギーに関するもの、資産、基金等のストックに関するものなどが含まれています。
指摘事項には、府省等別、事項別、観点別など様々な分類があり、公共工事関係の指摘として明確に選別や分類ができるわけではありませんが、本稿では、主なものについて簡単に紹介いたします。
なお、選別、分類、説明等の内容については筆者の個人的見解であり、会計検査院の公式見解を示すものではないことをお断りいたします。
また、国庫補助事業に係る事案の指摘金額は国庫補助金ベースで示しています。
1設計に関するもの
これらは、構造物に求められる所要の安全度が確保されていない状態となっていた事態や、経済的な設計を行っていなかった事態などです。
【不当事項】
<農林水産省>
- 山林施設災害関連事業等の実施に当たり、当初設計において、仮設工を任意仮設とし、仮設作業道作設等を早期に施工する必要があるなどとして、概算数量により積算することとし、切盛土量や大型土のうの数量を計上していたが、実際の施工数量は、当初積算時の概算数量よりも大幅に少なくなっていた。
そして、任意仮設であっても、当初積算時の想定と現地条件が異なるなどの場合は、必要に応じて設計変更を行うこととされていることから、現地における施工状況を踏まえると、設計変更をする必要があったのに、実際の施工数量に基づいた設計変更を行っていなかった。
したがって、実際の施工数量に基づくなどして、工事費を修正計算すると、契約額が割高となっていた。
[ 指摘金額 : 1239万円] - 農業用施設災害復旧事業の実施に当たり、護床工において、ブロックとブロックの間の中詰めの材料として適切でない粒径の小さな河床土砂を使用していて、吸出し防止策が十分に講じられていなかったため、流水の作用により中詰めした河床土砂が流失することによって、ブロックとブロックの間隙から埋め戻したブロック設置面の河床土砂が吸い出され、河床に洗掘が生ずるおそれのある構造になっており、現に、護床工の河床部分が洗掘され、全てのブロックが沈下している状況となっていた。
したがって、本件護床工は、設計が適切でなかったため、埋め戻した河床土砂が吸い出されて河床の洗掘が進行することにより復旧したエプロン等に損傷が生ずるおそれがあり、工事の目的を達していなかった。
[ 指摘金額 : 1億0993万円]
<国土交通省>
- 河川等災害復旧事業の実施に当たり、根固工の設計において、技術基準等で定められた根固ブロックの密度とは異なる値を用いて必要重量を算出したり、既設の根固ブロックが必要重量を満たしているか確認せずに再利用していたり、根固ブロック等の敷設高を変更した際に、必要敷設幅を算定することなく、変更前と同じ敷設幅としたりしていた。
さらに、根固工と護岸等との間に間隙が生ずる場合には適当な間詰工を施す必要があるのに、間詰工を施すこととしていなかったり、間詰工としては適当でない粒径の小さな土砂を用いてその間隙を埋め戻すこととしていた。
また、根固ブロックを護岸の基礎に接するよう敷設することとしていたが、設計業務の成果品である図面の間で整合しない部分があり、実際には根固ブロックを図面どおりに敷設することができない状況となっていたのに、監督職員に確認することなく施工し、根固ブロックを護岸の基礎前面から離れた位置に敷設していたため、根固工と護岸の基礎との間に間隙が生じていたが、間詰工を施していなかった。
このため、敷設された根固ブロックが必要重量や必要敷設幅を満たしていなかったことや、適当な間詰工を施していなかったことから、河床の洗掘が進行すると護岸等に損傷が生ずるおそれがある状況となっていた。
したがって、本件根固工は、設計又は設計及び施工が適切でなかったため、護岸等の基礎を洗掘から保護できない構造となっていて、本件護岸工、根固工等は、工事の目的を達していなかった。
[ 指摘金額 : 11件 1億5003万円] - 防災・安全交付金(その他総合的な治水)事業及び社会資本整備総合交付金(急傾斜地崩壊対策)事業の実施に当たり、待受式擁壁の設計において、衝撃力の算定の際に、急傾斜地の高さについて、誤って斜面全体の高さから擁壁背後の斜面に設置された法枠の高さを控除した高さとするとともに、安定計算の際に、衝撃力の算定では移動高を1.0 mと設定していたのに、誤って0.5 mとするなどしていたため、待受式擁壁に作用する力を過小に算定していた。
また、抵抗力の算定の際に、付着力に乗ずる擁壁底面の幅については有効載荷幅を用いる必要があるのに、擁壁底面幅をそのまま用いるなどしていたため過大に算定するとともに、図面作成の際に、誤って擁壁背面の裏込め土の高さを、安定計算の設定条件の高さより高く図示していたことから、衝撃力の作用位置が安定計算における位置より高くなっているなどしていた。
このため、いずれも衝撃力作用時において、滑動に対する安定については安全率が許容値を大幅に下回り、転倒に対する安定については合力の作用位置が転倒に対して安全であるとされる範囲を大幅に逸脱するなどしていた。
したがって、本件待受式擁壁は、設計が適切でなかったため、所要の安全度が確保されていない状態となっていた。
[ 指摘金額 : 2件 3169万円] - 防災・安全交付金(下水道)事業及び社会資本整備総合交付金(下水道)事業の実施に当たり、集水桝の設計において、誤って、自動車荷重の影響を考慮しない場合に適用する標準図を選定していたり、自動車荷重等の影響を考慮した応力計算を行っていなかったほか、側壁及び底版に配置する鉄筋について、設計計算書とは異なった配置間隔により配筋図を作成したりしていた。
このため、集水桝の一部については、底版の鉄筋に生ずる引張応力度が鉄筋の許容引張応力度を、側壁や底版のコンクリートに生ずる曲げ引張応力度が、コンクリートの許容曲げ引張応力度をそれぞれ大幅に上回るなどしていて、いずれも応力計算上安全とされる範囲に収まっていなかった。
したがって、設計が適切でなかったため、所要の安全度が確保されていない状態となっていた。
[ 指摘金額 : 2件 1238万円] - 河川等災害復旧事業の実施に当たり、橋りょうの支承部の設計において、レベル2地震動時における照査を行っていなかった。
そこで、レベル2地震動時における照査を行ったところ、橋台のアンカーバーに生ずる曲げ引張応力度は、曲げ引張応力度の制限値を大幅に上回っていて、設計計算上安全とされる範囲に収まっていなかった。
また、橋りょうについて、必要桁かかり長を確保するなどの落橋防止システムの検討を行っていなかった。
そこで、必要桁かかり長を算出すると、施工された本件橋りょうの現況の桁かかり長は、必要桁かかり長に比べて長さが不足しており、落橋防止システムの性能が確保されていない状況となっていた。
したがって、本件橋りょうは、支承部及び橋台の設計が適切でなかったため、上部構造の所要の安全度が確保されていない状態となっていて、橋台及びこれに架設されたPC桁等は、工事の目的を達していなかった。
[ 指摘金額 : 2505万円] - 河川等災害復旧事業の実施に当たり、水路工の設計において、現場打ちコンクリート水路を築造することとし、地下水位は低いと判断して、水路の浮上に対する検討を省略しても安全であるとしていた。
工事契約後に、現場打ちコンクリート水路からプレキャスト鉄筋コンクリート製のU型水路に変更したが、同様に、浮上に対する検討を行わずに施工していた。
しかし、水路内の水位は低下しやすい状況となっており、水路背面については、水が滞留し地下水位が上昇しやすい状況となっていた。
また、U型水路に変更したことにより自重が軽くなっているため、水路がより浮上しやすい状況となっていた。
そこで、本件U型水路について、浮上に対する検討を行ったところ、安全率は必要とされる安全率を大幅に下回っていた。
したがって、本件U型水路は、設計が適切でなかったため、所要の安全度が確保されていない状況となっており、U型水路及びU型水路上部の法覆護岸は、工事の目的を達していなかった。
[ 指摘金額 : 584万円] - 河川等災害復旧事業の実施に当たり、建設発生土の搬出先を検討する際に、 搬出距離が20.0kmとなる位置に最寄りの公営処分地が所在するとした上で、要領に基づき、当該公営処分地を搬出先として決定し、建設発生土を10 tダンプトラックにより搬出することとして設計し、これにより建設発生土を搬出していた。
しかし、搬出距離を計測するに当たり前提としていた搬出経路は、車幅が約2.5 mの10 tダンプトラックが通行できない道路を通行するものとなっているなどしていた。
そこで、通行が可能である搬出経路のうち、最短となる搬出経路の距離を改めて計測すると、20kmを超えていて、このような場合、当該工事現場から50km以内に所在する公営処分地と建設発生土を受け入れる民間処分地の中で、処分費等が最も安価となる場所へ搬出することなどとされている。
そして、最寄りの公営処分地に搬出する場合と最寄りの民間処分地に搬出する場合の処分費等を比較すると、後者の処分費等の方が安価となることから、要領に基づき、これを搬出先として決定すべきであった。
したがって、本件建設発生土の処分費等は、搬出先の決定に係る設計が適切でなかったため、最寄りの民間処分地を搬出先として設計した場合と比べて過大となっていた。
[ 指摘金額 : 455万円]
<阪神高速道路株式会社>
- 橋りょうの耐震補強工事の実施に当たり、これに係る設計業務において、会社は、「道路橋示方書・同解説」(示方書)とは別に独自に基準を定め、鋼製橋脚に係る耐震補強の要否の判定等については全て当該基準を適用することとしているのに、大阪管理局は、示方書を適用するよう委託業者に指示していた。
その結果、改めて当該基準を適用してやり直す結果となり、示方書を適用して実施した鋼製橋脚に係る耐震補強の要否の判定及びそれに基づく成果品は耐震補強工事に使用されていなかった。
したがって、示方書を適用して実施した成果品が所期の目的を達していなかった。
[ 指摘金額 : 1999万円]
<日本下水道事業団>
- 水路橋の耐震補強工事の実施に当たり、落橋防止システムの選定(可動支承部)について、橋座部を拡幅して必要な桁かかり長を確保すれば落橋防止構造は省略できるとして設計し、施工していた。
しかし、本件水路橋は、単純橋が連続するものであり、両端が橋台に支持されている一連の上部構造を有する橋ではなく、橋軸方向に大きな変位が生じにくい構造特性を有する橋とはみなされないことから、落橋防止システムとして落橋防止構造を設置する必要があった。
また、落橋防止構造の鉄筋の定着長(固定支承部)について、鉄筋コンクリート製の落橋防止構造を設置していたが、鉛直方向の鉄筋の基本定着長は、鉄筋の許容引張応力度等から算出した長さ以上とすることとなっているのに、誤って応力計算上の鉄筋に生ずる引張応力度等から算出して設計し、施工していた。
そこで、適切な定着長を算出すると、本件の定着長はこれに比べて長さが不足していた。
したがって、本件水路橋の落橋防止システムは、設計が適切でなかったため、地震発生時に水路橋を構成するボックスカルバートの所要の安全度が確保されていない状態となっていて、工事の目的を達していなかった。
[ 指摘金額 : 530万円]
【処置済事項】
<国土交通省>
- 橋りょう工事における床版防水工の設計について橋りょう工事における床版防水工の設計に当 たり、設計条件等により特定の床版防水層を使用しなければならない特段の理由がなく要求性能を満たす床版防水層の候補が複数あるにもかかわらず、経済性を比較検討して最も経済的なものを選定していなかった事態が見受けられた。
[ 指摘金額 : 7759万円]
<東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社>
- プレキャストコンクリート床版等の非破壊試験の頻度について
橋りょうのプレキャストコンクリート製の床版及びその接合部の設計に当たり、鉄筋のかぶりを確認するための非破壊試験について、プレキャスト床版の非破壊試験の頻度がプレキャスト床版の特徴及び製作状況を考慮したものとなっていなかった事態及び床版接合部の非破壊試験の頻度が床版接合部の構造等を考慮したものとなっていなかった事態が見受けられた。
[指摘金額:東日本高速道路株式会社2650万円、中日本高速道路株式会社2340万円、西日本高速道路株式会社6120万円]
2 積算に関するもの
これは、大型ブロックの1㎡当たりの単価の算定を誤ったため、工事費が割高となっていた事態です。
【不当事項】
<農林水産省>
- 農村地域防災減災事業の実施に当たり、取付護岸を改修する護岸工において、1㎡当たりの大型ブロックの設置費について、ブロック1個当たりの材料単価を、1㎡当たりの単価に換算するために1㎡当たりで使用する個数で除し、これに1㎡当たりの設置に要する労務費等を加えて算定していた。
しかし、ブロック単価を1㎡当たりの単価に換算するためには、ブロック単価に1㎡当たりで使用する個数を乗ずるべきであり、これに基づき修正計算すると、本件工事費は割高となっていた。
[ 指摘金額 : 258万円]
3 経理に関するもの
これは、交付の対象とならない国費率等差額の交付を受けていた事態です。
【不当事項】
<国土交通省>
- 砂防えん堤又は排水施設を整備等する事業の実施に当たり、通常の国の負担割合が引き上げられることなどとされている開発指定事業に該当するなどとして、通常国費率等による各年度の交付金等精算額に当該年度の引上率を乗じて得た額から交付金等精算額を減じた額について、国費率等差額として交付申請を行い、同額の交付を受けていたが、一級水系等河川の流域で実施したため開発指定事業に該当するとして交付申請していた実施箇所は一級水系等河川の流域外にあったこと、また、一級水系等河川の流域外における事業を開発指定事業として交付申請していたことから、本件事業は、国費率等差額の交付の対象とは認められない。
[ 指摘金額 : 3件 1億3369万円]
4 維持管理等に関するもの
これらは、耐震性能を評価するために必要な耐震性点検を実施していなかった事態や、補助事業により取得した道路用地の財産処分に係る手続が適正でなかった事態などです。
【不当事項】
<農林水産省>
- 農村地域防災減災事業の耐震性点検の実施に当たり、管理する農道橋の点検業務において、5年に1回の頻度で実施することとしている農道橋の損傷等の状況を把握するための定期点検として、現況調査のみを実施しており、耐震性能を評価するために必要な耐震診断等の耐震性点検は実施していなかったことから、本件補助事業は、補助の対象とは認められない。
[ 指摘金額 : 2件 1150万円]
<国土交通省>
- 都市構造再編集中支援事業の実施に当たり、都市計画道路を新設するため、補助事業で取得した道路用地について、国土交通省の承認を受けずに、民間会社に対して駐車場用地として使用を許可していて、補助金適正化法第22条の貸付けに当たる財産処分を行っていた。
そして、これにより使用料を収納していたため、国庫納付の条件が付される場合に該当するのに、国庫納付を行っていなかった。
したがって、本件道路用地に係る国庫補助金交付額及び収納した使用料のうち国庫補助金相当額は財産処分に係る手続が適正でなかった。
[ 指摘金額 : 7054万円]
【意見表示・処置要求事項】
<国土交通省>
- 多重無線回線の機能維持に必要な通信鉄塔及び局舎の耐震性等の確保について
国土交通省は、災害発生時における迅速な被災情報の把握等を実現することを目的として、光ファイバ通信回線と多重無線回線とを組み合わせた統合通信網を全国的に構築している。
同省本省、地方整備局等及び河川国道事務所等は、建物の屋上や地上に鉄塔を設置し、当該鉄塔等に、空中線、多重無線装置等の通信設備を設置している(以下、これらの鉄塔を「通信鉄塔」、通信鉄塔が屋上に設置されている建物を「局舎」)。
そして、同省は、災害発生後、被害状況等の情報の収集及び連絡に統合通信網等を用いることにしている。
また、同省は、診断基準を制定するなどして、既存の通信鉄塔及び局舎の耐震診断を行うこととしている。
診断基準等によれば、耐震診断の結果、診断基準において定められている通信鉄塔の健全性又は局舎として必要な耐震性が不足することが確認された通信鉄塔及び局舎については、耐震補強工事を実施するなどの耐震性等を確保するための対策を立案して、適切な措置を実施しなければならないこととされている。
しかし、通信鉄塔及び局舎について、耐震診断が実施されていないなどしていて耐震性等が確保されているか不明な状態のままとなっていたり、耐震診断の結果、耐震性等が確保されていないと確認されたのに耐震対策が実施されていなかったりなどしていて、大規模地震が発生した際等に多重無線回線の機能が維持できないおそれがある事態が見受けられた。
[ 背景金額 : 26億3240万円]
【処置済事項】
<国土交通省>
- 下水道管路施設の老朽化対策の実施状況について
下水道管路施設の老朽化対策に当たり、腐食環境下にある下水道管路施設を適切に把握していなかったり、点検を行っていなかったりなどしていて、下水道管路施設の持続的な機能確保や効率的な維持・修繕等に支障が生ずるおそれがある状況となっている事態が見受けられた。
また、下水道管路施設の機能や状態の健全さを示す指標である緊急度がⅠと判定された下水道管路施設については、緊急度Ⅱと判定された下水道管路施設より異状の程度が高いものであり、速やかに修繕等を実施する必要があったのに、これを実施していないなどの事態が見受けられた。
[ 背景金額 : 4億4298万円] [ 指摘金額 : 2850万円]
以上に紹介した事例を含め、令和4年度決算検査報告の指摘事項等については、全文を会計検査院のホームページの「最新の検査報告」(https://www.jbaudit.go.jp/report/new/index.html) に掲載しています。
過去の検査報告についても、データベースで検索できますので、是非御活用ください。
今後とも、検査活動に対する皆様の御理解を深めていただくため、検査の結果をできる限りわかりやすく公表するとともに、事態の再発防止のため、説明会等の機会をとらえて検査結果について説明してまいりたいと考えております。
最後になりましたが、国や地方公共団体、国の出資法人等の職員の皆様及び公共工事に携わる関係者の皆様には、これらの検査報告事例を参考にしていただければ幸いです。
【出典】
積算資料2024年2月号
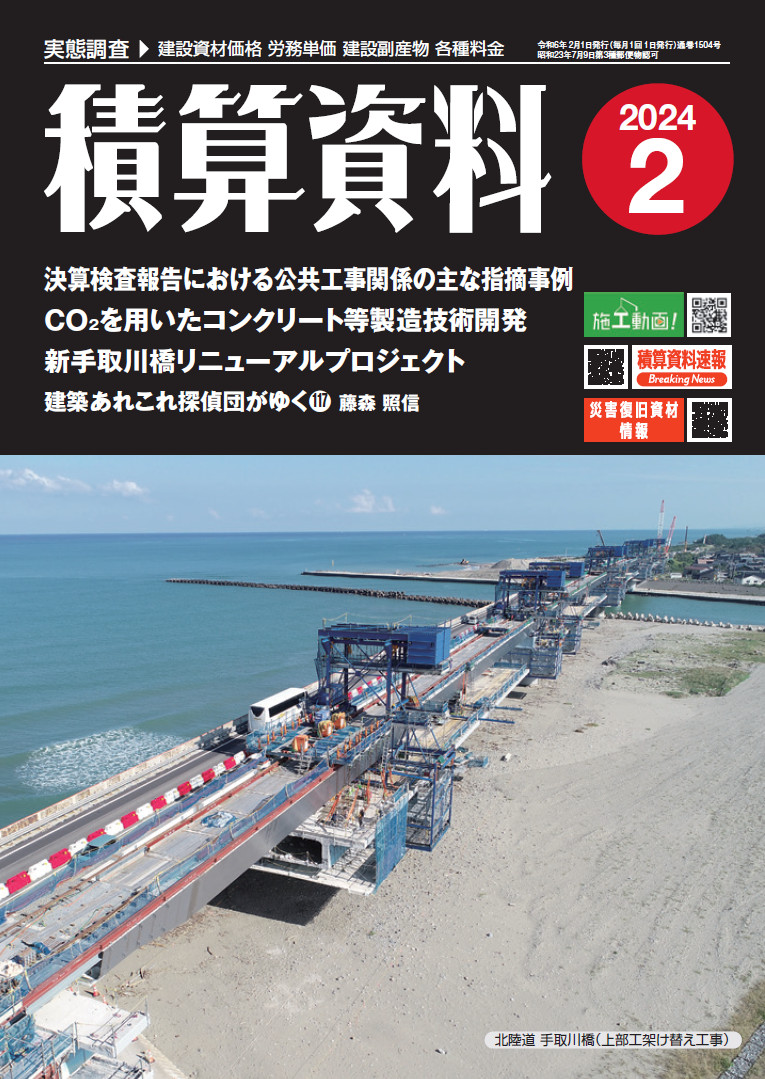
最終更新日:2024-05-14
同じカテゴリーの新着記事
- 2026-01-26
- 積算資料
- 2026-01-05
- 積算資料
- 2025-12-22
- 積算資料
- 2025-12-01
- 積算資料
- 2025-11-25
- 積算資料
- 2025-11-05
- 積算資料
- 2025-10-27
- 積算資料
- 2025-10-20
- 積算資料