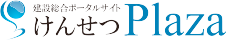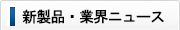- 2019-01-16
- 特集 「いい建築」をつくる材料と工法 | 積算資料公表価格版
はじめに
LVL(Laminated Veneer Lumber:単板積層材)は,丸太をかつらむきのように薄く切削(ロータリーレース)した単板(べニア)を積層した木質材料である。「べニア」というと合板のことと思うかも知れないが,べニアは一層一層の薄い2〜3mmの単板のことを示し,これを繊維の向きに交互に直交するように積層したものが合板であり,繊維の向きが平行になるように積層したものがLVLである。それぞれ同じ単板から構成される木質材料ではあるが,構成が少し異なっている。単板は,幅2m程度の丸太から加工できるため,長い直材(柱材であれば3m)を必要としない点で,小曲り材などの丸太(B材)にも対応しやすく森林資源の有効活用として有効である。
1. 線材と面材
木材は,樹木から丸太,さらに製材して角材になって建築に用いられるため,通常は棒状の線材として用いられることになる。このため,木造住宅も柱,梁といった線材を組み合わせた軸組構造が日本では古くから用いられてきた。こうして線材を垂直,水平に組み合わせた架構が木造建築の架構美として評価されてきており,大規模な集成材建築でも線材による架構形式が用いられてきた。
構造用材料としてのLVLは,これまで大断面集成材のライバルとして大規模木造建築への適用が考えられてきたが,現実的には幅120mm,せい360mm,450mmといった住宅用製材と同様の断面が主流になっていた。しかし,こうした断面のLVL部材の実際の製造方法は,一旦厚さ120mm,幅1200mmの大きなLVLの板を製造し(写真-1),1200mmの幅を600×2や450×2+300などに切り分けて製造する。つまり,1200mm幅の厚いLVLの板が製造段階の途中で製作されていたのである。
このままの大きさで用いれば,現在,厚板木質面材として注目を浴びている直交集成板(CLT)と同様の木質材料として用いることができるのである。
つまり,構造材としてのLVLの特徴は,線材として柱や梁として使用できること,さらに厚板面材として壁や床としても使用できることであり,LVLによる都市木造は,線材と面材を用いた多層の建築と考えることができる(写真-2,3)。
さらに,都市木造の実現に向けて構造性能,防耐火性能の検証が進むLVLであるが,魅力ある都市木造としては,仕上げ材としての木質材料である。LVLの意匠材としての特徴は,その製造方法から生じる木目面と積層面という全く異なる2つ表情をもっていることである。これまでは,製造の効率性から表面は,木目面の使用に限定されていたが,その木口に見られる積層面が特徴的であることからその表情を生かした積層面を表面としたパネルも生産され始めた(写真-4)。こうして構造性能,防耐火性能を維持したまま,その独特な表情をした木質面材「木層ウォール」が登場することになった。「木層ウォール」は,1時間準耐火耐力壁,30分準耐火非耐力壁,1時間準耐火非耐力壁の大臣認定を取得しており,都市部での3階建ての木造建築においてLVLの表面を「あらわし」で使用することができるようになっている。
2. LVLを用いた建築
LVLに着目して,NPO法人team Timberizeと全国LVL協会では,2015年より「T-1グランプリ」と同時に「T-1 LVL賞」としてLVLを活用した都市木造を表彰している。これまでの住宅用流通製材の代用品としてだけでなく,LVLの特性を活かした都市型の建築を選定している。
歴代の受賞作品を紹介すれば,LVLを用いた都市木造の挑戦を知ることができるだろう。
■T-1 グランプリ 2011
木が“見える,触れる”というのは,木造であることの重要な要素である。上棟時,約900mmピッチで架けられた小梁が整然と並んでいる様子や,柱を両側から梁によって挟み込んだ架構は,大きな断面を作るのが難しい木造ならではの美しい構造であった。しかし,残念ながらこれらは全て石こうボードの耐火被覆で覆われてしまい見えてこない。設計者も残念な思いであったのではないだろうか。見せる「木造」をどう作るか? の回答を,LVLパネルによる耐震壁で実現している。鉄板のフレームにLVLパネル(カラマツ)をはめ込んだハイブリッド的な耐震壁である。LVLパネルの性能をフルに利用するため,パネルと鉄板フレームとの接合部に工夫と苦労の跡が垣間見られる。
■ T-1 グランプリ 2015
この建物では,長方形の単純な平面に列状ながら一見不規則に並べられた柱と,あえて空間の中央に配置された柱。壁ではなく柱が空間を不明瞭に分割する。列柱が,屋根架構に潜む明確な構造システムを暗示させている。壁・桁などの線で支持する場合には,梁は1方向(ワンウェイ)のシステムが採用されやすいが,点の柱で支持する空間では,2方向(ツーウェイ)で活用するのが自然である。さらに平面の直交座標系に対して角度を振ることによって出隅部分の軒の処理を合理的にしている。構造的には,単位面積あたりの屋根荷重から必要な梁の本数が算出可能で,その配置リズムは自由になり,ここでは「1/fゆらぎ」のリズムで並べることができる。重ね格子梁では構造性が大きくなりがちであるが,天井懐空間の遮音,振動防止,防火,設備活用などと合わせて工夫ができれば,この単純な構造システムの組み合わせによる単位空間の構成は,都市木造に求められる多層構造にも生かしやすい。
CLTなどの厚板面材と大断面集成材の中間の薄くて,せいの高い梁は,LVLの得意分野になっていくだろう。こうした工夫が木質厚板工法の中でも比較的薄い30〜60mm厚の面材の新しい活用につながることが期待される。
■ T-1 LVL賞 2015
LVLの厚板の壁が前面道路に向かって象徴的に並んでいる。その潔さとスケール感はまちの景観を生み出していく都市木造の一つの形を提示している。待合室である吹き抜け空間も印象的である。大きな木のヴォリュームに包まれているにもかかわらず,LVL積層面の特徴的なテクスチャーと斜めに傾けられた壁面,そしてスリットから差し込む光によって開放感も併せ持つ空間になっている。
建物は準防火地域の3階建て動物病院である。建物用途が畜舎となるため,準耐火建築物で,正面は1時間準耐火構造の大臣認定を取得したLVL厚板外壁(木層ウォール),その他の部分は,柱・梁を準耐火構造告示の石こうボード等で耐火被覆している。LVL厚板だけで構成すると配線・配管スペースの確保など困難なことも多いため,柱・梁の軸組とLVL厚板の併用工法となっている点が特徴的である。この建物では特に積層面を積極的に見せて,木材の新しい意匠を作り上げている。特に,雨掛かり部分では構造躯体のLVLを「あらわし」にせず,仕上げにもう一枚LVLを張っており,この仕上げが劣化した場合にも取り替えられるように配慮されている。都市において木材を内外装の仕上げに使うお手本になる建物といえる。
■T-1 LVL賞 2016
LVLとSPFを組み合わせたモノコック構造で,それぞれの部材は必要性能に応じ適材適所で使用されている。さまざまな木質材料をフラットに評価,選定し,論理的かつ合理的に組み合わせるというそのコンセプトはとても明快で,原理主義に陥りがちな木造建築とは一線を画するものであり,これからの木造建築に求められる姿勢であろう。このハイブリッドな木質構造の中で,LVLがその特質を生かして役割を果たしている。
このようなディテールがもたらす繊細な架構とは対照的に,空間構成は非常にシンプルで力強く,その絶妙なバランスの上に成立している建築デザインが秀逸である。
3.接合
LVLの構造材が意匠材として「あらわし」で用いられるようになると,接合部も単に必要な応力を伝達するだけでなく,見え方も重要になる。きれいな接合金物で表現することもできるが,防耐火性能を考えると,LVL部材の内部に仕込まれた接合金物が必要とされ,厚板,大断面のLVLの接合では,GIR(グルードインロッド)との相性がよい。「T-1 ホームコネクター賞」では,そうした組み合わせの例が多くみられる。
■T-1 ホームコネクター賞 2016
間口の狭い細長い敷地に建つ3階建ての住宅である。建築家の自邸ということで,創造力を大胆に現実化できる意欲的な作品である。1階がRC,2・3階が木造で,各階ともLVLの厚板を用いた薄肉ラーメン構造を採用している。接合部に引張力を負担させることができるホームコネクターを使うことで,実現可能な構造形式である。
木造部分が150×900という薄い断面で弱軸ラーメンを実現していることに技術的大胆さを感じるが,細長い敷地を有効利用できる構造形式であり,地震力の大きさや,耐久性を考慮して1階をRCにしている点は非常に合理的である。
おわりに
LVLの厚板を用いた壁,壁柱といった使い方から面材としての折版構造,線材としての重ね格子梁とさまざまな構造形式に適用されている。しかし,LVLは万能の木質材料というわけではない。今後は製材と集成材,CLTを適材適所に組み合わせながら,木質材料の特徴を生かした都市木造の整備が望まれる。
【出典】
積算資料公表価格版2018年11月号

最終更新日:2023-07-10
同じカテゴリーの新着記事
- 2026-01-21
- 特集 コンクリートの維持管理 | 積算資料公表価格版
- 2026-01-21
- 特集 コンクリートの維持管理 | 積算資料公表価格版
- 2025-12-19
- 特集 上水・下水道施設の維持管理 | 積算資料公表価格版
- 2025-12-19
- 特集 上水・下水道施設の維持管理 | 積算資料公表価格版
- 2025-12-19
- 特集 上水・下水道施設の維持管理 | 積算資料公表価格版