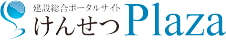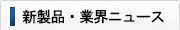- 2016-05-06
- 積算資料公表価格版
夜間の避難路の確保
1993年(平成5年)の北海道南西沖地震は、
マグニチュード7.8という巨大地震であり、発生からわずか数分で巨大津波が奥尻島を襲った。
夜間だったことも災いして死者172名、行方不明者26名(奥尻町)という甚大な犠牲が生じたことで、
暗闇避難の問題がクローズアップされた。
暗闇避難の対策として、LED照明によるソーラー電源灯付き標識の設置が推奨されているが、
不日照点灯期間、設置場所に応じた耐候性・耐久性の検討、定期的な保守点検(蓄電池の交換など)が適切でなければ、
緊急時に点灯しないリスクもある。
「蓄光材料」は、日中に太陽光などを蓄光し、夜間に発光するもので、津波避難誘導の観点から大きな関心を集めている。
ただ、従来の蓄光材料は屋内用が主流で、屋外での使用を想定した性能基準は整備されていなかった。
蓄光材料とは何か
蓄光材料は、いささか専門的な表現になるが、JISでは
「中間エネルギー準位に蓄積されることにより、遅延したフォトルミネセンスをりん光といい、りん光を発する色材を蓄光材料という」
と定義され、りん光とは、一般に光励起後に100μs以上持続するルミネセンスを指す(JIS Z9101)。
蓄光材料の明るさは、りん光輝度(単位:mcd/㎡)で示される。
蓄光材料を屋外で使用する場合、側溝や水路への転落防止といった日常的な用途であれば、
ほとんど人が歩いていない真夜中まで発光している必要はないかもしれないが、
津波はいつ何時発生するかわからず、一晩中発光している必要がある。
わずか数時間で発光が消えてしまうようでは困るのだ。
また、沿岸部は塩害を受けやすく耐候性、耐アルカリ性、耐摩耗性など厳しい性能が要求される。
蓄光材料のJIS規格の変遷
蓄光材料のJIS規格は、当初、JIS Z9107(安全標識-性能の分類、基準及び試験方法)において、
蓄光材料の最低りん光輝度などが規定されていた。
その後、蓄光材料の輝度や耐候性などについて抜本的な見直しが行われた結果、
JIS Z 9096・9097が相次いで制定され、屋外での避難用蓄光式表示に関する中心的な規格となっている。
JIS Z 9096床面に設置する蓄光式の安全標識及び誘導ライン
建物からの避難を容易にするため、
屋内および建物につながる屋外の床面、階段、階段の壁面などに設置する
蓄光式の安全標識ライン及び誘導ラインについて規定している。
耐候性、耐水性、耐湿性、耐摩耗性、耐薬品性などの規定を強化し、りん光輝度の設置場所での測定方法を示している。
JIS Z 9097津波避難誘導標識システム
津波が発生したときに安全な場所(津波避難場所、津波避難ビル)に避難する際に利用される
津波避難誘導標識システムについて、津波標識に記載する図記号、方向矢印などの記載例を具体的に規定。
さらに、暗闇対策として、蓄光材料を屋外で使用する際の性能および試験方法を世界で初めて規定した。
蓄光材料のりん光輝度の区分を次のように規定している。
Ⅰ類:3mcd/㎡以上10mcd/㎡未満
(高輝度)
Ⅱ類:10mcd/㎡以上(超高輝度)
(励起停止後720時間後のりん光輝度)
なお、現在、「JIS Z9098 災害種別避難誘導標識システム」もパブリックコメントの段階に入っている。
洪水・内水氾濫・高潮・津波・土石流・崖崩れ・地滑り・大規模な火事など種別ごとの避難誘導を規格化したものだ。
詳細はそれぞれのJIS を参照されたい。
蓄光材料の市場動向
内閣府では自治体に対して、これらの新JIS規格に沿った素材の使用を推奨している。
ただ、蓄光材料市場では現在、旧JIS品が多数流通しており、新JISに対応した製品は少ない。
とりわけ、超高輝度のⅡ類となると、極めて少数である。
新JISの厳しい性能基準は、気候条件の厳しい沿岸地区で、いつ津波が起きてもいいように一晩中発光させるためには、
この水準の性能が必要不可欠ということであり、その趣旨を深く理解する必要がある。
蓄光材料の採用に際しては、新JISへの対応を十分に確認し、
何より人命がかかっているということを肝に銘じて適切に判断すべきであろう。
【出典】
月刊 積算資料公表価格版2016年3月号
特集 防災減災・国土強靱化に貢献する技術
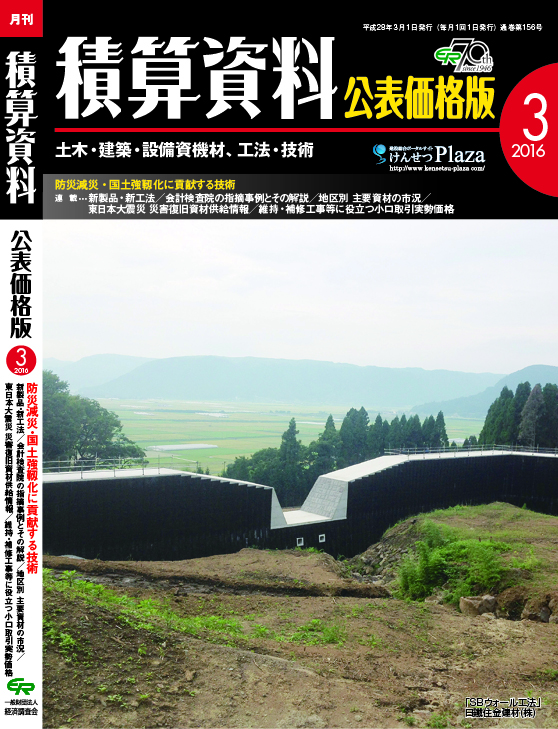
最終更新日:2024-10-30
同じカテゴリの新着記事
- 2025-03-19
- 特集 道路の安全・安心 | 積算資料公表価格版
- 2025-02-20
- 特集 防災減災・国土強靭化 | 積算資料公表価格版
- 2025-02-20
- 特集 防災減災・国土強靭化 | 積算資料公表価格版