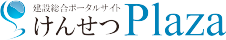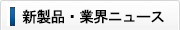- 2024-10-21
- 特集 「いい建築」をつくる材料と工法 | 積算資料公表価格版
1. 電気自動車と充電
近年、各種メディアを見ていると、電気自動車(EV)を扱った記事をよく目にします。
新しいEVが登場した、充電ステーションが新設された、充電の従量課金が始まった、EVの火災事故が起きた、などです。
そこで今回は、EVとはどういうものか、充電はどうなっているのかを紹介しながら、施設設計や建築を担われている方々の参考になるようまとめてみたいと思います。
1-1. EVとその近縁車両のシステムから見た分類
EVと言ってもその種類はいくつもあります。
定義については世の中にさまざまな意見がありますが、本記事では以下のように定義します。
EVとされるものには、バッテリー(充放電できる電池:二次電池)に蓄えた電力でモーターを駆動して走る「バッテリー式電気自動車(BEV)」、バッテリーの電力で走るが、電力が足りなくなると搭載している小型内燃エンジンで発電して電力を補って走行を続けられる「レンジエクステンダー付き電気自動車」、バッテリーのほかエンジンも搭載していて、エンジンは発電だけでなく走行に使うこともある「プラグイン・ハイブリッド車(PHEV・PHV)」などがあります。
EVと似たものに、日産自動車株式会社が発売している「e-power」搭載車がありますが、これは走行はモーターだけで行うものの、積んでいるバッテリーはEVに比べて容量が小さく、外部から充電する機能を持っていません。
よって走行エネルギーはすべてエンジンから供給されるため、いわゆるEVの分類には入らないとされることがあります。
本田技研工業株式会社やトヨタ自動車株式会社が21世紀になる直前に世に出した「ハイブリッド車(HV)」も、走行エネルギーを結局は内燃機関に依存していることから、同じようにEVのカテゴリーには入らないとされることがあり、まとめると、以下のようになります。
EV…BEV、レンジエクステンダーEV、PHEV・PHV
内燃車…e-power搭載車、HV
1-2. 充電する電気から見た分類
EVは外部から電力を受け入れられる、つまり充電できる能力が一つの特長です。
その充電に使う電気には、私たちが家庭で使っている交流(AC)だけでなく、直流(DC)の2つがあります。
EVに充電するということは、バッテリーに充電することを意味し、バッテリーへは最終的にはDCを用いて充電することになります。
家庭のACから充電できるEVには、ACをDCに変換できる装置が車内に積まれています。
また、EVに使われるモーターには、高度な制御ができる交流モーターが使われているので、バッテリーのDCをACに変換するインバーターもEVには積まれています。
インバーターが電流量や周波数を幅広く制御できるお陰で、EVは滑らか、かつ力強く、さまざまな速度で走ることが可能となっています。
それでは、EVにはどのような充電の形態があるのでしょうか。
以下にまとめてみます。
①普通充電
「普通充電」という言葉がよく使われていますが、じつはこれに対する定義は特にありません。
とは言え、家庭などに来ている交流(AC) 100V・200Vを使って充電することを、一般に普通充電と呼ぶ形が定着しています。
街中を歩いていると、カーディーラーの店先に、青地に白文字の看板で「EV 200V CHARGING POINT」と書かれた看板を目にすることがあります。
このように普通充電ではAC200Vを使うものが中心となっています。
普通充電は電流(A)、電圧(V)とも高くないものを使うため、EVのバッテリーを、例えば満充電するには数時間から、バッテリー容量によっては10時間を超す時間がかかることもあります。
日本では3kW出力が普及しており、筆者の自宅にも3kWの普通充電設備がありますが、近年ではより短い時間で充電できる6kW出力設備も充電スポットや宿泊施設などでは整備され始めています。
電流、電圧が低めのため、充電時にバッテリーの温度を上げにくい特長があり、またじっくり充電するなかで「セル・バランス(電池モジュール間の不均衡)」を整えられる点もメリットです。
なお、1970年代半ば以降に建てられた住宅には、たいていAC100VだけでなくAC200Vも引き込まれているので、EV用普通充電器を住宅に追加することは比較的容易にできます。
②急速充電
普通充電とは異なり、短い時間で大きな電力量を充電するために用いられているのが急速充電です。
これには直流(DC)が使われます。
世界で最初のDC急速充電規格である「CHAde MO規格」のEVが個人向けに販売を開始したのは2010年のことでした。
同年7月の三菱自動車工業株式会社の「i- Mi EV(アイ・ミーブ)」に続いて、12月には日産自動車株式会社のLEAF(リーフ)が登場しました。
この2車種は世界初の量産・市販EVでした。
この時代の急速充電はDC400Vに125Aが最大として設定されていました。
400V×125Aなので50,000W、つまり50kWとなります。
もちろん、EVの電池の状況から、つねに50kWの電力が受けられるわけではありませんが、50kWまでの出力の充電器が続々と登場しました。
2023年頃から急速充電器はさらに出力を上げ、90/120/150/180kWといったものが市中に設置され始めています。
2024年9月現在、幹線級の高速道路のSAやPAには、4~6口といった複数口を持つ高出力の急速充電器がもはや珍しくなくなってきています。
急速充電の長所は、短い時間で大きな電力量を充電できることです。
この点で、後に述べる「経路充電(移動の途中で必要な電力を継ぎ足す充電)」を行う際には欠かせない充電形態です。
逆に短所は、充電器と施設が高額になる点です。
前述の普通充電に比べると、施設の維持費もずっと高額となります。
まとめると以下のようになります。
普通充電…普通充電器(AC100/200V)で行う充電
急速充電…急速充電器(DC400Vなど)で行う充電
1-3. 充電する場面から見た分類
EVの充電は、使用される場面でも分類されます。
それぞれの場面で、AC200Vによる普通充電が向いていたり、逆にDC急速充電が向いていたり、両方の設置が可能なこともあります。
①基礎充電
自宅や勤務先などで、EVが長時間駐車しているときに行う充電は「基礎充電」と呼ばれます。
長い時間をかけて充電できるので、AC200Vによる普通充電が向いているとされます。
充電設備が安価に設置でき、充電中の電力負担も小さくて済むのが利点です。
近年では、企業によっては社員の福利厚生の一環として普通充電器を敷地内に数多く設置する例も出始めています。
スマートフォンのように、帰宅したら充電器につないでおけば、翌朝には満充電で使えるという点で、EVユーザーにはまさに基礎となる充電方式と言えるでしょう。
従来はマンションのような集合住宅では設備が設置しにくいことが問題となっていました。
とくに機械式駐車場では設置が困難という事情もありましたが、こうした問題を解決し、充電のマネジメントまでケアしてくれる会社が多く生まれています。
②経路充電
中長距離の移動や旅の途中では、目的地まで走るのに足りない電力を途中で補給することになります。
これが「経路充電」です。
移動の途中に行うので、充電は迅速に行いたいものです。
よって、経路充電の中心は急速充電となっています。
高速道路のSA・PAや、一般道なら道の駅などに充電器が置かれ、経路充電の利便性を確保しています。
カーディーラーに置かれている急速充電器も、経路充電の役割を担っていると言えるでしょう。
③目的地充電
移動の目的地、たとえば旅行の際の宿などで行う充電を「目的地充電」と言います。
目的地までの移動で消費した電力を補ったり、翌日の移動に備えて電力を蓄えるものです。
宿泊を伴うものだけでなく、例えばショッピングモールやゴルフ場などのレジャー施設や、病院、買い物に行くスーパーマーケットでの充電も、この目的地充電に含まれるとされています。
宿泊する場合は、充電のための時間が比較的長く取れるので、普通充電ができるAC200V充電器(普通充電器)が用いられることが多いようです。
設備の設置にあまり費用がかからないのと、充電器を設置した施設の電力供給にあまり大きな負担をかけずに済むというメリットがあります。
一方、目的地充電に急速充電器が用いられることもあります。
滞在時間が比較的短く、多くの人が入れ替わりに使う場面が想定されるコンビニエンスストア、ショッピングモール、スーパーマーケット、病院、市町村役場などに置かれることがあります。
まとめると以下のようになります。
基礎充電…自宅などで行う充電
経路充電…移動・旅の途中で継ぎ足しで行う充電
目的地充電…移動・旅・買い物・レジャーの目的地で行う充電
2. 世界の急速充電(直流)
かつて世界には、EV充電用のDCを使った急速充電は存在しませんでした。
EVの実験車両はいくつも作られていましたが、いずれもACによって充電されていました。
世界で初めてDCによる急速充電を国際的に規格化したのが、今日も日本で使われているCHAde MO規格であり、その始まりは2014年春のことでした。
このとき、CHAde MOを参考に欧州と北米が企画して提案したコンボコネクタを用いたCCS規格も、国際規格に採用されました。
その後、中国で作られたGB/T、そして米国のテスラ(Tesla、Inc.)が作ったTPC(テスラ独自コネクタ、今後はNACSになる)が加わり、世界のDC急速充電規格が出揃いました。
今では、さらに高出力で充電できるChaoJi(次世代CHAdeMO)とMCS(次世代CCS)も、DC急速充電規格として完成しています。
トラックやバス、船舶などへの充電を目指しています(図-1)。
3. 互換性の維持―互換性テストセンターを用いた不具合解消
近年、EVの種類が増え、急速充電器の種類も増えてきましたが、これに伴って増えて来たのが、組み合わせの際に出る小さな不具合です。
このためCHAde MO協議会では、さまざまなEVと急速充電器との互換性を確認する「チャデモ・マッチングテスト・センター」を、検定機関である株式会社UL Japanとのコラボで2024年3月に三重県に開設しました。
EVと急速充電器の組み合わせによっては充電できないなどといった不具合の発生を未然に防ぎ、日本国内における円滑なEVの普及推進を目指すためです。
こうしたテストセンターが常設されるのは、世界でも初めての試みです。
これに先立ち、2023年12月には、開発中の車両などをシミュレーターを使って試験するビークル・テストセンターを、チャデモ協議会では株式会社東陽テクニカと認証機関であるテュフラインランドジャパン株式会社と協力して東京都内に開設しています。
チャデモ協議会では認証機関テュフラインランド社と協力し、長野県にも互換性をテストするセンターを計画しています。
今後も、EVと充電器の組み合わせによって起きる不具合の解決を目指します。
【出典】
積算資料公表価格版2024年11月号
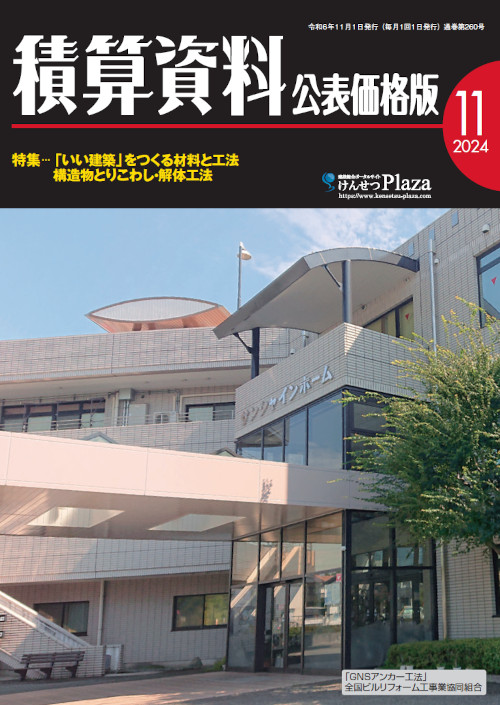
最終更新日:2025-07-07
同じカテゴリーの新着記事
- 2026-01-21
- 特集 コンクリートの維持管理 | 積算資料公表価格版
- 2026-01-21
- 特集 コンクリートの維持管理 | 積算資料公表価格版
- 2025-12-19
- 特集 上水・下水道施設の維持管理 | 積算資料公表価格版
- 2025-12-19
- 特集 上水・下水道施設の維持管理 | 積算資料公表価格版
- 2025-12-19
- 特集 上水・下水道施設の維持管理 | 積算資料公表価格版